-
11月28日 第4時限目
- 公開日
- 2012/11/28
- 更新日
- 2012/11/28
授業研究・研究発表会
6・7組(特別支援学級) 国語
6組も7組も、フラッシュ型教材で国語の勉強をしています。6組はひらがなを文字と絵を組み合わせながら確認しました。7組はことわざを確認しました。声に出しながら短い時間で勉強してきたことを繰り返し復習するのは、このフラッシュ型教材がとても有効です。みんなでフラッシュ型教材に取り組んだあとは、一人一人に応じた学習をしていきました。
どちらの学級も、授業の流れをはじめに目で見える形で確認しています。安心して分かりやすい授業のための工夫です。 -
11月27日 第3時限目
- 公開日
- 2012/11/27
- 更新日
- 2012/11/27
授業研究・研究発表会
1年算数 ひきざん
繰り下がりのあるひき算について、「10といくつ」という数の仕組みのよさを使いながら、(十何)−(1位数)を手際よく計算したり、文章問題を解いたりする学習です。
本時は、減数が5または、5より小さい数のひき算の仕方を考える授業です。
はじめに、絵と問題文から場面を把握して、式を立てます。そして、数図ブロックを操作して計算の仕方を考え解いていきます。1年生で合い言葉になっている「サクランボ」により、10といくつにするために、減数をいくつといくつに分けるのかを表します。そして、話形に沿って説明しながら問題を解いていきます。
問題は「くりが13こあります。4こたべるとのこりはなんこですか」。
2つの考え方
ア 10かた4をひいて6 6と3で9
イ 13から3をひいて10 10から1をひいて9
がありますが、どちらの方法も「10からひく」ということをみんなで確認して解いていきました。
そして、練習問題では、確認し合った「10からひく」をつかって問題を解きました。
習得したことを練習してさらに確実に使えるようにすることが大切です。
-
11月26日 第3時限目
- 公開日
- 2012/11/26
- 更新日
- 2012/11/26
授業研究・研究発表会
4年算数 小数×整数、小数÷整数
既習の計算や小数の意味を用いて、(小数)×(整数)、(小数)÷(整数)について、0.1の個数に着目することによって、整数と同様に計算できることを説明したり、計算の仕方を理解しながら計算する学習です。
本時は、液量を考えることから、(小数)×(整数)の学習について関心をもち、言葉の式を基にして、小数に整数をかける計算について考え、説明しながら計算の仕方を身につけ練習する学習です。
0.2×4を0.1のいくつ分を元に考えて、
0.2は0.1が2個
0.2×4は0.1が(2×4)個
だから
0.2×4=0.8
という求め方をみんなで習得し、
その後、0.3×4や
0.03×4についても、0.1や0.01がいくつ分で考えればよいことを、
言葉の式に表して説明しながら解きました。
ただ計算できればよいのでなく、考え方を説明できることが大事になっています。
練習問題では、どの子も集中して問題を解き、即時評価により確認できました。
-
11月21日 「学習指導」研究発表会記事
- 公開日
- 2012/11/26
- 更新日
- 2012/11/26
授業研究・研究発表会
11月21日に開催しました「学習指導」研究発表会について、朝日新聞、読売新聞、中日新聞に記事が掲載されました。CCNetでも11月29日に当日の様子や、講師の堀田龍也先生のインタビューなどが放映される予定です。
-
11月21日 「学習指導」研究発表会
- 公開日
- 2012/11/22
- 更新日
- 2012/11/22
授業研究・研究発表会
11月21日「学習指導」研究発表会を実施しました。
市内や愛日地方管内を中心に、県内・県外からも550名を超える教育関係者にご参会いただきました。
本校が昨年度より取り組んできた「みんなで思考・判断・表現し合える子の育成-確実な習得と伝え合う活動・学び合う活動を通して」の研究テーマのもと、全25学級ので授業を公開しました。授業では、出川小で日常的に行っている、全ての子どもたちの学力を保障するために、全校で統一して学習規律を整え、ICT活用により確実な習得をはかり、その習得したことをもとに活用をはかる様子を観ていただきました。子どもたちはいつもと同じように学習に集中していました。
公開授業後は、全体会で出川小の取組を発表するとともに、尾張教育事務所武田指導主事より、
・全校統一の学習規律、学習スキルのよさ
・ICTの効果的活用のよさ
・習得、活用する授業への取組について
・分かりやすく表示し伝えることの大切さ
を中心にご指導賜りました。
そして、昨年度より指導・助言をいただいている玉川大学教職大学院教授堀田龍也先生からは、演題「毎日の授業で確実な習得と活用をはかる学習指導」をもとに、次のように出川小の取組を価値付けしていただきながら、参会者にご講演いただきました。
○出川イズム(出川小の取組の価値は)とは、どの教室も当たり前のことに、愚直に取り組んでいることである」
・当たり前のことを毎日続けることが大事
・継続したICT活用で効果が現れる
・場数を踏まずに上手になることはあいえない
・誰にでもできることを、全員で徹底して続けることが簡単なようで難しい
・指導技術はこれまでもこれからも変わらない、便利なICTを組み合わせることで効果がある
・教科書を大事な教材としたい
・板書したことを、子どもがノートに書くは基本中の基本
・ICTは道具ではなく環境である
・児童は内容を理解し考えを持てば(確実な習得があれば)、自信を持っていくらでも話し合うこと(活用すること)ができる。そのようする授業・指導が大事。
出川小にとっては大きな節目として、研究発表会を開催し、無事終了することができました。多くの関係者、保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご支援に心より感謝申し上げます。研究はまだまだ途中です。子どもたちにとってさらによいものとなるように地道に取り組んでいきます。 -
いよいよ明日が本番です… 〜研究発表会〜
- 公開日
- 2012/11/20
- 更新日
- 2012/11/20
授業研究・研究発表会
明日・11月21日(水)は、出川小学校の「学習指導」研究発表会の日です。昨年度と今年度の2か年、学習指導についての研究委嘱を受け、研究を進めてきましたが、現段階での成果を発表する日になります。
今日の午後、全体会を行う体育館をはじめ、各教室や運動場などで、たくさんの来校者をお迎する準備を整えました。あとは明日の本番を迎えるのみです。どうか良い天候で明日を迎えたい…そう願っています。
≪明日来校される皆様へ≫
明日は、いつも通りの出川っ子たちの姿と、いつも通りの授業を見ていただけたらと思います。どうかお気をつけてお越しください。
≪出川小学校のみなさんへ≫
たくさんのお客様がいらっしゃいますが、いつも通りの授業ができるよう、がんばりましょう。お弁当が必要です…忘れないようにしましょうね。 -
11月20日 第2時限目
- 公開日
- 2012/11/20
- 更新日
- 2012/11/20
授業研究・研究発表会
1年算数 かたちづくり
色板や棒を使ったり点をつないだりして、形を構成にきづきながいろいろな形をつくる学習です。
本時は、色板を並べて、形を作り、できた形を互いに発表し合いながらどんな形がつくられているか話し合う授業です。
三角や四角の色板を使いますが、その2枚の組み合わせで「三角2枚での四角」「三角2枚での三角」「三角2枚でのひねり(菱形や平行四辺形に近い形)」がどのようにできているかという観点でできた形をについて話し合います。
知らず知らずの内に作っている形も、構成されてるもとがあることに気づいていきます。
一方、使った形を実物投影機で大きく映し出すと、子どもたちも発表しやすく、また、話し合いもどこのことを伝えているのかが分かりやすいよさがあります。
1年生でも、指示棒を使いながら分かりやすく、伝え合っています。 -
11月19日 第5時限目
- 公開日
- 2012/11/20
- 更新日
- 2012/11/20
授業研究・研究発表会
2年算数 かけ算(2)
アレイ図を使いながら、九九を整え、習得した九九を使って、それを適用して問題をとく学習です。
本時は、かけ算を使った問題をドリルを使いながら解いていく学習です。
「1本18円のひご7本と、80円のねんどを買いました。みんなで何円でしょう」について、
ア 問題に線を引き整理をする
イ 図に表す
ウ 式を考える
エ 説明しする
という流れで、全員で解いていきます。
ただ単に「勉強したところだから自分で解きましょう」ではなく、1問目は、全員で「はじめに、ひごの値段をもとめます」「次にひごとねんどのねだんをたします」などを確認し、かけ算とともに、たし算もつかいながら答えを求めていきます。
そして、2問目は同じような問題で一人一人でとく部分を増やしていきます。
さらに、問題を進めていく中なかで、「さっきの問題と同じようにやれば出来そうだ」ということをもとに、自信を持って一人で解いていくことが出来るようにしていきます。
-
11月16日 第5時限目
- 公開日
- 2012/11/16
- 更新日
- 2012/11/16
授業研究・研究発表会
4年社会 きょう土を開く 木曽三川分流工事と愛知用水
地域の発展につくした先人の働きについて、先人の足跡を見学・調査したり、年表などの資料を活用したりして調べ、地域の人々の願いや努力、先人の働きや苦心によって地域の生活が向上してきたこと理解したりしながら、地域社会への愛情をもって、よりよい発展について考えていく学習です。学習の教材としては、木曽三川分流工事や愛知用水が対象です。
本時は、愛知用水の概要や水をうまく通すための工夫について習得し、完成後の人々の生活について調べる授業です。
まずはじめに、かがやく大愛知(副教材)で愛知用水の概要を知りました。長野県牧尾ダムから、知多半島まで112kmにもおよぶ中で、様々な地形を経ながら通っている愛知用水をよりイメージするために、大型の地図と特徴的な地形での現地の写真の大写しより明確につかみました。そして、もう一度、本文から地形による工夫をつかみや、発表し合い整理し、それら大がかりな工夫により、島のくらしが豊かになったことを確認し合いました。
概要をつかみ、具体的な部分に焦点を当て、それらを整理していくことで、愛知用水全体の工夫が、人々の生活に結びついていることを確実に習得させることがポイントです。
-
11月15日 第2時限目
- 公開日
- 2012/11/15
- 更新日
- 2012/11/15
授業研究・研究発表会
5年社会 工業生産と工業地域
我が国の工業生産や工業地域の様子に関して、主な工業生産の種類、工業地域の分布や工業を支える運輸などの働きについて調べながら、工業生産が国民生活を支える重要な役割を果たしていることについて、地図・統計・写真などの資料を活用して必要な情報を集め、我が国の工業生産や工業地域の特色や現状を読み取って理解したり、まとめたりする学習です。
本時は、日本の工業を支える運輸業の役割を調べる授業です。地図を見て、様々な交通機関との位置関係やそれらの広がりについてとらえます。まずはどの地図でそれらのことが確認できるのかを、各自で探します。ただし、地図帳は地域が広範囲で情報が満載です。速やかに必要な地図にたどり着けない子どももいます。その様なときは、子どもの様子に応じて実物投影機で全員で共有する地図を示します。そうすることにより、工業がさかんな地域と交通機関の位置関係を確認し合うことが可能になります。
どの情報(地図)が、この学習に必要なのかをはっきりさせていくことはとても大切なことです。
-
11月14日 第4時限目
- 公開日
- 2012/11/15
- 更新日
- 2012/11/15
授業研究・研究発表会
6年社会 長く続いた戦争と人々のくらし
日中戦争、我が国にかかわる第二次世界大戦、その頃の国民生活とそれらにかかわる代表的な文化遺産について、我が国が戦時体制に移行して、敗戦によって国民が大きな被害を受けたことや、戦場になった地域に大きな損害を与えたこと、それらにかかわる代表的な文化遺産の意味などを、文化財・地図や年表・戦争を体験した人の話、その他の資料などを活用して調べ、我が国が戦時体制に移行して、敗戦によって国民が大きな被害を受けたことを理解しながら、自分の考えを明らかにしていく学習です。
1つのクラスでは、東京大空襲を中心に日本各地の都市は、空襲によってどのような被害を受けたのかについて、もう1つのクラスでは、沖縄戦や広島・長崎への原爆投下を中心に戦争はどのようにして終わったのかを学習しました。
教科書に示されている写真や図、そして、東京大空襲を体験した方の話の資料や、女子学生(ひめゆり隊員)たちの手記の資料により、その事実を確認しました。子どもたちは、資料を食い入るように確認していました。資料の内容は、とてもインパクトがありますが、だからこそ、その事実を元に自分たちの立場でしっかり考えていくことは、とても大事な取組です。 -
11月12日 第5時限目
- 公開日
- 2012/11/13
- 更新日
- 2012/11/13
授業研究・研究発表会
4年音楽 いろいろな音色を感じ取ろう せんりつのとくちょうを感じ取ろう
題材「もみじ」について、次のようなことをめあてに主旋律と副次的な旋律を歌詞唱する学習です。
○範唱を聴いて曲の感じをつかむ
○歌詞内容に合わせて、主旋律をなめらかに歌う
○音程やリズムに気を付けて副次的な旋律を歌う
○旋律が重なり合う響きを聴き合いながら合唱する
○互いのパートの声を聴き合いながら歌う
○発音や発声、息つぎに気を付けて歌う
○パートを交替して響きを確かめ合いながら合唱する
本時は、これまで歌ってきたことのまとめをしました。
ひとり、もしくは2人でたしかめの歌を歌ったり、ワークでこの楽曲の歌詞や特徴の確認をしました。
季節の移り変わりを感じながら、日常の中で口ずさんでいく曲になっていくでしょう。 -
11月9日 第2時限目
- 公開日
- 2012/11/09
- 更新日
- 2012/11/09
授業研究・研究発表会
2年算数 かけ算(2)
アレイ図(たて横9ますずつの図)を使い、かける数が1増えると積はかけられる数だけ増えること理解したり、九九を唱え、それを使って問題を解いたりする学習です。
本時は、6のだんの九九づくりです。
アレイ図を2枚の紙で必要なところだけ○が表れるようにずらしながら、6のだんでは6づつ増えることを実感しながら6のだんの九九を構成していきます。
そして、九九としても声に出して唱え、十分になれながら、6のだんを使った問題をといていきます。
これまで勉強してきた、5のだん・2のだん・3のだん・4のだんとはかけられる数の大きさが違うので、アレイ図で確認しながら確実に習得できるようにしていきます。
アレイ図でも、声でも、そして式でも、それぞれのだんの九九を覚え活用していくことができるようにしていきます。 -
11月8日 第1時限目
- 公開日
- 2012/11/08
- 更新日
- 2012/11/08
授業研究・研究発表会
3年算数 計算のじゅんじょ
かけ算の順思考を組み合わせた問題を、計算法則により1つの式で表すことを考えて問題解決の場で活用する学習です。
「ジャングルジムと木と校舎の高さをくらべました。ジャングルジムの高さは2m、木ノ高さはジャングルジムの3倍、校舎の高さは木の高さの2倍。校舎の高さは何mですか」
考え方は2つ。
・先に木の高さを計算して求める
・先に校舎の高さはジャングルジムの高さの何倍かを計算して求める
それぞれのよさを確認しながらも、どちらも1つの式で表すことことができることを知り、「多くの数をかけるときには、計算する順序をかえても答えは同じ」というかけ算のよさを確認し合いました。
そして、そのことをもとに、別の問題でも、計算の順序はちがっても、答えは同じであることを使って練習をしました。
1時間の単元ですが、これまで学習して習得してきたことを元に、授業全体では活用しながら、かけ算のあらたなよさを習得し、さらに練習問題でそのことをいつでも使うことができるようにしました。今後の単元でもこのよさを使っていきます。
-
11月 朝会
- 公開日
- 2012/11/08
- 更新日
- 2012/11/08
今日の学校
11月8日 朝会を実施しました。
まずは、表彰伝達。春日井市明るい社会づくりの会実践体験文、健全育成大会関係、環境問題絵画コンクール、赤い羽根共同募金児童生徒作品コンクール、読書感想文コンクールで優秀な成績などをおさめた子どもたちが、校長先生より表彰状などをうけとりました。そして、いろいろな場面での活躍をみんなで拍手により称えました。
校長先生からは、6年生の修学旅行のがんばりとこれからの課題についてのお話の他、5つ全校に伝えられました。
1 登校時のポケットに手を入れて歩いている姿について
歩行のバランスには手の振りは必要です。
とっさの時に手が出ないと大きなけがになるので気をつけましょう。
2 交通安全について
愛知県、春日井市ともに交通事故が昨年よりも多い。
絶対に交通事故なわないように気をつけましょう。
3 ボールなど使ったものの扱いについて
クラスのボールがいくつも落ちていたと届けられたままになっている。
自分たちで使ったもの、自分たちのものは、大切にしましょう。
4 運動場での遊び方
縄跳び、ケイドロ、ボール遊びで運動場がいっぱいで、危険です。
縄跳びをする場所を運動場の校舎側に決めて遊びます。
5 11月21日の多くのお客さんが来校することについて
いつも通りの授業を観てもらいましょう。
そうじで学校をきれいにしましょう。
その他、毎月取り組んでいるあいさつ運動への呼びかけが、児童会の係の先生よりありました。
全校で、充実した11月にしていきましょう。 -
11月7日 第5時限目
- 公開日
- 2012/11/07
- 更新日
- 2012/11/08
授業研究・研究発表会
5年社会 わたしたちの生活と工業生産 自動車をつくる工業
我が国の工業生産は国民生活を支える重要な役割を果たしていることを理解するとともに、その発展を考える学習です。そのために、我が国の工業生産に関する学習課題について、的確に調査したり、地図や地球儀・統計などの各種基礎的な資料を活用したりして調べたことをまとめたり、適切に表したりしていきます。その中でも、自動車産業を中心に学習を進めます。9月に訪問した豊田の工場での見学が生かされます。
本時は、自動車産業について、これからどんなことを調べていくのか明確に持ちながら、自動車づくりについて、資料をもとに概要をつかみました。
教科書などの資料をもとに、その内容をつかむことはとても重要な学習活動です。日本のどの辺りで自動車づくりが多く行われているのか、その割合はどのくらいか、豊田市周辺にある自動車関連の工場の多さやその理由を、地図やグラフなどから的確につかみ、事実を元に自分なりの考えを明らかにしていきます。
地元愛知の自動車産業について、興味を深めながら学習を進めていきます。 -
修学旅行を終えて
- 公開日
- 2012/11/07
- 更新日
- 2012/11/07
修学旅行
今日(7日)の3限から、6年生は通常の授業に戻りました。楽しかった修学旅行の話を友だちと話す姿が印象的でしたが、若干の体調不良者があったものの、おおむね健康で元気よく登校してくれました。
昨日の解散式の中でも話題になりましたが、今回の修学旅行に向け様々な準備をしてきました。今後も目標に向かってこつこつと準備をしていくことの大切さをかみしめながら学校生活をおくってほしいと思います。また、集団での行動時のマナーや、ONとOFFの切り替えなど、課題としてのこったことを少しでも達成できるようにしてほしいと思います。
-
修学旅行 無事に終了!
- 公開日
- 2012/11/06
- 更新日
- 2012/11/06
修学旅行
11月5日・6日の2日間、京都・奈良方面に出かけていた6年生の修学旅行ですが、6日夕方に、参加者全員無事に帰校しました。
この2日間は最初から最後まで、子どもたちが行動する時間帯はずっと曇天でしたが、傘は1回も使うこともなく、天候に恵まれた形で進めることができました。近畿地方は6日の早朝に、比較的激しい雨が降り、宿舎周辺では雷鳴も鳴り響きましたが、子どもたちの天気運は相当なもので、雨にぬれることなく旅行を続けることができました。
帰校につきましては、保護者の方々にお迎えをしていただきました。お忙しい中、ありがとうございました。今日は6年生の子どもたちからたくさんのお土産話が聞けるかと思います。どうか子どもたちの楽しかった2日間の様子を聞いてあげてください。
なお、明日(7日)は6年生のみ時間をずらしての登校になります。体調を整えて、安全に気をつけながら登校してください。今日はしっかり身体を休めて、明日元気よく登校してくださいね。 -
修学旅行1日目
- 公開日
- 2012/11/05
- 更新日
- 2012/11/05
修学旅行
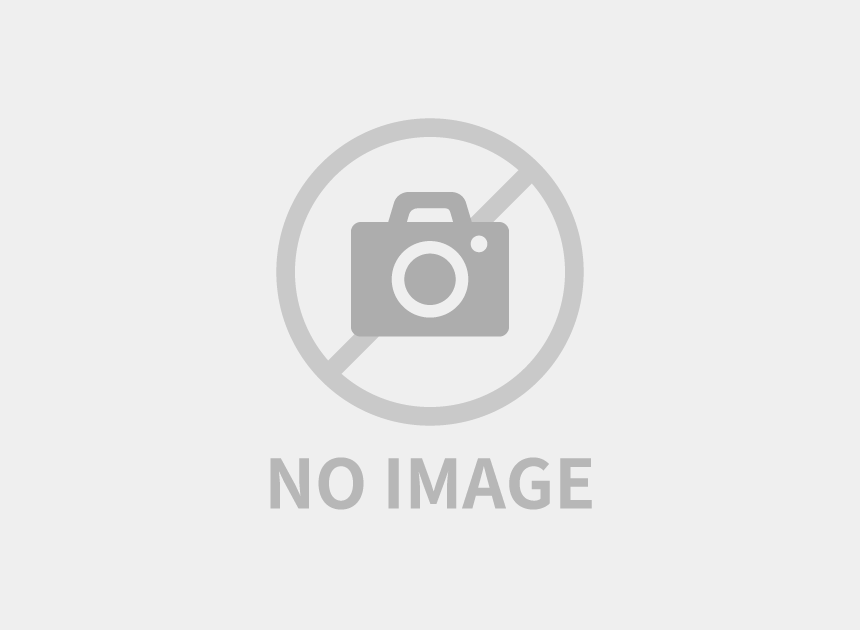
11月5日、6年生修学旅行1日目です。予定より,少し遅れて7時前ぐらいに、全員無事に宿に到着しました。足を痛めた児童が2名ほどいるようですが、みんな元気です。心配された天気も、今日1日なんとか大丈夫だったようです。明日も元気に活動できることを祈っています。
-
11月5日 第3時限目
- 公開日
- 2012/11/05
- 更新日
- 2012/11/05
授業研究・研究発表会
4年国語 言葉について考えよう 文と文をつなぐ言葉
文と文をつなぐ言葉について、文と文の意味のつながりや接続語の役割を考えながら、接続語を適切に使うことができるようにする学習です。
本時は、つなぎ言葉の働きや使い方をまとめ、短文作りをする授業です。
つなぎ言葉(接続詞)である「だから・それで・そのため・しかし・それでも・でも・けれども・また・そして・しかも・それとも・あるいは・または・つまり・要するに・例えば・では・ところで・さて・いっぽう」などを使いながら、状況にあった文にしていきます。
また、本時は「書く」活動が多くあります。文をしっかり書き、つなぎ言葉の性質を整理するためには、しっかり整理されたノートが大切になります。例えば、□で言葉を囲ったり、線を引いたりしますが、定規を使って引くことを習慣にしています。そのためには、教師も分かりやすく板書をしたり、実物投影機で大きく映して、整理のポイントを分かりやすくしたりしています。
全員が整理されたノートになるよう、ねばり強く取り組んでいきます。



