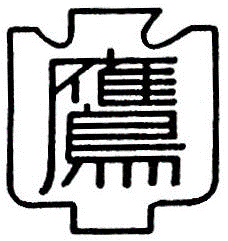-
平成21年度修了式
- 公開日
- 2010/03/24
- 更新日
- 2010/03/24
校長室から
修了式 式辞
おはようございます。今日は学年の締めくくり、修了式です。まず、今日までの一年間のことを振り返ってください。そして、次の一年をどう過ごすかを考えてください。
昨年の修了式でも話しましたが、有名な中国の古典、儒教の基本テキストである五経の筆頭に挙げられる経典 易経(えききょう)という書の中に、「君子は豹変す」「小人(しょうじん)は面(おもて)を革(あらた)む」と言う言葉があります。
豹の毛が季節に合わせて抜け変わり、美しい斑文となることから、君子つまり立派な人は、たとえ過ちを犯しても素早く善に立ち戻れるとか、君子は、時代の変化に合わせて自分を素早く的確に変えていけるという意味です。現代風に捉えれば、「誤りに気づいたら、素早く今までの意見を改めたり、行動のパターンを転換してよい」という意味です。
「君子は豹変す」の後の「小人(しょうじん)は面(おもて)を革(あらた)む」小人つまり、たいしたことのない人間は、変われるが、それは「表面的なもの」にとどまるという意味です。
確かに、私たちは過去のあやまちや自分のこだわりに引っ張られて意識や態度、生き方をすぐに変えられないものです。「こうありたい」「ああなりたい」と思いながらも、結局同じような毎日を過ごしてしまっている。では、そんな自分を大きく変えるにはどうすればいいのか。それには、大きな環境の変化を利用するのが一番効果的だといわれています。つまり、学年が一つ進級し、クラスも変わるこの時期こそが、最も自分を変えられる時期だということになります。 義務教育を終えて、自ら進路を選択しなければならない時期がまた一歩近づいてきます。今のままの生活態度でよいのか、選択の幅を広げるためにも、社会で通用する人間となるためにも、この機会に自分を見直し、よりよい自分を目指してください。
4月の始業式にはいい方向に豹変した姿を見せてください。
-
ホトトギスの川柳と親子関係
- 公開日
- 2010/03/23
- 更新日
- 2010/03/23
校長室から
平成21年度も明日の修了式を残すのみとなりました。
本年度の本校の教育活動も保護者の皆様、地域の皆様のお力添えにより、円滑に推進することができたと思います。ありがとうございました。
さて、年度の締めくくりに保護者の皆様方向けに、以下の話を紹介したいと思います。
社会の歴史分野などで学習した戦国時代を終結させた郷土の三英傑、信長・秀吉・家康の三人を覚えていますか。その天下を統一した戦国武将三人の性格をよくあらわしている「ホトトギス」を季語にした三つの川柳があります。
『鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス』 (織田信長)
『鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス』 (豊臣秀吉)
『鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス』 (徳川家康)
それぞれの武将の性格をよく表現していますが、このホトトギスをわが子に置き換えて考えてみてください。自分の親子関係は三人の句のうちどの内容に最も近いと思いますか。信長の句は児童虐待ですから論外だとしても、秀吉タイプは結構多いのではないでしょうか。また、子育てにおいて正解に近いといわれる家康タイプの方も多いかと思います。しかし、この三つ句の中には、真の親子関係を表すものはないと思います。なぜならば、実は三人ともホトトギスは鳴くものと決め付けているからです。確かに鳥は美しい声で鳴くことを求められています。しかし、鳴かない鳥は認められないのでしょうか。
昭和の実業家、経営の神様といわれた松下電器(パナソニック)の創始者、松下幸之助さんは、この三人を例えた句を真似て、自分なりのホトトギスの川柳を詠んだといわれています。
『鳴かぬなら それもまた好(よ)し ホトトギス』
簡単に説明すると、鳴かなくても、それ自体、よいものだ。鳴けないのならそれでもいいのだよ、そこにいてくれるだけでもいいのだよ、というメッセージでしょう。難しいかもしれませんが、再度ホトトギスをわが子に置き換えて考えてみると、どうでしょう。
いつも松下さんの句のような気持ちでいることは難しいと思いますが、根底にはこの気持ちを忘れないでいてほしいと思います。
-
小学校の卒業式
- 公開日
- 2010/03/19
- 更新日
- 2010/03/19
校長室から
春にふさわしい好天に恵まれた19日、市内の各小学校で卒業式が行われました。
鷹来中校区の鷹来小、大手小、西山小の3つの小学校の卒業式には、中学校を代表して、校長と教頭、教務主任が参加しました。
どの学校の卒業生もさすが最高学年にふさわしい立派な態度で、式に臨んでいました。立派に成長した子どもたちを見ていますと、その背景には、これまでの12年間注いでいただいたご両親の深い愛情や、6年間学習・生活両面でお世話してくださった小学校の先生方の強い思いなどが感じられました。
この卒業生を、4月から新入生として本校に迎えると思うと、その責任の重さに身の引き締まる思いがします。この子たちが充実した中学校生活を送れるように、迎える中学校側もしっかりと努力しなければならないと思いました。
卒業生の皆さん おめでとうございます。
4月から元気に鷹来中へ登校してください。
-
卒業式 式辞
- 公開日
- 2010/03/08
- 更新日
- 2010/03/08
校長室から
平成21年度 卒業証書授与式 校長式辞
春風に吹き出し笑う花もがな
この芭蕉の句に詠まれたように、花の開花を誘うような春の息吹が校庭のあちこちに感じられるこのよき日に、平成二十一年度卒業証書授与式を迎えることができました。
本日は、ご多用の中、ご来賓の皆様には、早朝よりご臨席いただきまして誠にありがとうございます。高いところからではありますが、お礼申し上げます。
さて、百五〇名の卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。今、あなた方一人一人に卒業証書を手渡しました。その一枚の紙の中には実に様々なものが宿されています。小学校から通算しての義務教育九年間。その長い年月、元気に登校し、基礎・基本の学習を身につけた皆さんの努力。それを絶えず見守り、世話をしてくださったご両親の愛情。そして皆さんの成長のために、ある時は厳しく、ある時は優しく導いてくださった先生方の情熱、安全に登下校できるようにと見守ってくれた地域の皆様方の思いなど。多くの人達の陰のご苦労の積み重ねによってはじめて手にすることができた卒業証書なのです。感謝の気持ちを忘れないでください。
皆さんは、この一年間、最高学年としてリーダーシップを発揮し、在校生のよき手本となりました。また、学校の顔として対外行事にも出場し、全力を尽くし、活躍してくれました。その活動ぶりは、在校生にしっかりと受け継がれて行くことでしょう。
在校生の皆さん。皆さんは、先輩が築いてくださった輝かしい伝統とよき校風をしっかりと受け継ぎ、さらに発展させるよう努力してください。
卒業の門出に当たり、みなさんにひとつお話をします。知っている人も多いと思いますが、ミスターチルドレンの「終わりなき旅」という曲があります。卒業というものは確かにゴールではありますが、新しいスタートでもあります。まさに「終わりなき旅」です。一〇年ほど前に発表されたこの曲の中には心にしみる言葉がたくさんあります。卒業するあなた方に贈る話として、本日この場で、その歌詞を紹介します。
「終わりなき旅」 櫻井和寿
(歌詞省略)
このような歌詞です。この歌詞の中から皆さんに、三つのフレーズを贈りたいと思います。
一つ目
「高ければ高い壁の方が 登った時気持ちいいもんな
まだ限界だなんて認めちゃいないさ」
人間に限界があるとすれば、それはあきらめたときです。困難な課題に直面したとき、これは無理だとすぐにあきらめるのではなく、やれるかもしれない、いややれる、やってやると、自分の力を信じて、工夫と努力を重ね、それを解決する気力を奮い立たせてください。
二つ目
「誰の真似もすんな 君は君でいい
生きる為のレシピなんてない」
義務教育を終え、これからは自分で選んだそれぞれの道を歩んでいくのです。マニュアルどおり、型どおりに進めるものではありません。それぞれの人生の主役それは自分です。みんなちがってみんないいのです。
三つ目
「いいことばかりでは無いさ
でも次の扉をノックしよう
もっと素晴らしいはずの自分を探して」
人生には失敗や挫折はつきものです。しかし、そこで立ち止まるのではなく、自分の可能性を信じて、もう一度前に進んでください。未来は無限の可能性を秘めています。失敗から学ぶことは山のようにあるはずです。失敗をゴールと見るのではなく、新たなスタートと考えればいいのです。
以上、三つのフレーズを取り上げました。一つでもいいですから、自分の胸に留めておいてください。この曲には、そのほかにも力を与えてくれるフレーズがたくさんあります。つらいとき、迷ったとき、少し落ち込んだ気分になったとき、ぜひこの曲を思い出して、気に入ったフレーズを口ずさんでみてください。
さて、最後になりましたが、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。たくましく成長されたお子様の晴れ姿をご覧になり、さぞお喜びのことと拝察申し上げます。今日まで学校にお寄せいただきました温かいご支援ご協力に対しまして、心から感謝申し上げます。
また、地域の皆様方、日ごろから鷹来中学校を地域の学校として、ご支援いただきありがとうございます。卒業生は地域の未来を担っていく大切な人材、地域の宝だと思います。十五歳、まだまだ人間としては未熟ですので、さまざまな機会に、社会で共生していくためのルールやマナーなどご指導ください。そして、今後も在校生同様、温かい見守りや声掛けをお願いいたします。
以上、卒業生の皆さんの限りない前途を祝し、式辞といたします。
平成二十二年三月八日
春日井市立鷹来中学校長 伊藤 孝之
-
いじめ問題について
- 公開日
- 2010/03/04
- 更新日
- 2010/03/04
校長室から
いじめ問題は、社会状況の急激な変化を背景に、子どもたちを取り巻く環境と心の発達の問題が、複雑に絡み合った根の深い問題であります。しかし、児童生徒の人権にかかわる重大な問題であり、すべての学校に起こりうること という認識のもとに、職員一同、その根絶 に向けて全力で取り組んでいます。
いじめの多くは学校で発生しています。はじめはふざけのように見える小さないじめであっても、集団化を伴い次第にエスカレートし、脅し、ゆすり、暴力といった事態に発展することもあります。いじめを予防 するとともに、早期発見 が必要だと思います。
HPの右側の「生徒指導」 の欄には県教委「いじめの発見・解決・防止をめざして−小さなサインが見えますか−」 をリンクしてあります。一度クリックして、内容を見てください。 その中には、学校での対応だけでなく、家庭や地域での対応 方法も示されています。以下に一部紹介しておきます。
Q5 家庭や地域では、どんなことからいじめが発見できますか?
自分がいじめられていることを知られると、親が悲しい思いをするだろうと思って、子どもは親には相談しないことが多いものです。しかし、家庭や地域でもさまざまな形でサインとして表れます。保護者や地域の大人は、子どもたちの発する次のようなサインを注意深く感じ取る必要があります。
ア 家庭では
○ 食欲がなくなる。
○ 口数が少なくなり、学校のことや友達のことを話さなくなる。
○ 衣服が汚れていたり、けがをして帰宅したりすることが多くなる。
○ いらいらしたり、おどおどして落ち着きがなくなったりする。
○ 弟や妹、ペットなどをいじめるようになる。
○ 家族に対してかたくなになってくる。
○ 助けを求めるうわ言を言ったり、不眠を訴えたりするようになる。
○ 身体や持ち物の外からは見えない部分に落書きがされている。
○ 親が出ると何も言わずに切れてしまうような不審な電話がたびたびかかる。
○ 不良じみた友達が訪ねてくることがある。
○ 携帯電話に友達からの呼び出しメールが頻繁に入る。
○ 外出しなくなり、人におびえるようになる。
○ 学校から帰ってから、友達と遊ぶことが少なくなる。
○ 家の金銭を持ち出したり、買い与えたものがなくなったりする。
○ 登校時間になると頭痛、腹痛などを訴え、登校を渋るようになる。
○ 学校へ行きたくないと言いだすことが増える。
○ メモや日記などに悩みが書き込んであったりする。
○ 遅刻したり、早退したりすることが多くなる。
○ 転校したい、生まれ変わりたい、などともらすようになる。
イ 地域では
○ 同じ子が、何度も自転車の修理にやってくる。
○ 公園や街角で、個人を中傷した落書きをよく見る。
○ いつも同じ子が飲食物などを買いに使い走りされている。
○ 登下校ときにいつも同じ子が他の子のカバンや用具等を持たされている。
○ いつも同じ子が笑い者にされたり、からかわれたり、命令されたりしている。
○ プロレスごっこなどの遊びによく加えられている。
○ 公園や神社で大勢に囲まれ、罵声を浴びせられたり暴力を振るわれたりしている。
Q6 我が子がいじめに加わっていないか心配ですが?
「子どもは親の鏡」と言われるように、親の普段の言動は、子どもに大きな影響を与えます。親が地域のいろいろな人と分け隔てなく仲良く関わる姿を見て育った子どもは、友達とのかかわりを大切にします。日ごろから子どもに思いやり、やさしさ、正義感などを育むよう努め、いじめる側にならない子どもにしたいものです。 次のような様子が見られたら、いじめに加わっていないか注意する必要があります。
○ 買い与えていない物品を持っている。
○ 心当たりのないお金を持っている。
○ 言葉遣いが乱暴である。
○ 親と顔を合わせたり、会話したりすることを嫌がる。
○ 年下や自分より弱い立場の子に対して高圧的である。
○ 勉強さえできればいいといった言動がよくある。
○ 友達の名前を呼び捨てにし、友達を手下のように使っている。
○ 他人を馬鹿にしたり、悪口を言ったりする。
○ パソコンや携帯電話で、他人を非難するメール等を書き込んでいる。
○ 特定のグループでの行動が多く見られる。
○ 特定の子を無視したり、仲間はずれにしたりしている言動が見られる。
学校・家庭・地域 の連携によって、子どもたちが安心して楽しく通える学校が成り立つと思います。今後とも、よろしくお願いします。
-
新入生説明会
- 公開日
- 2010/02/17
- 更新日
- 2010/02/17
校長室から
2月15日(月)新入生説明会を行いました。本年度は中学校の様子を知ってもらおうと、説明会の前に30分程度、1年生の授業を公開しました。雨の中でしたが、多くの方に参加いただきました。
新入生説明会校長あいさつ
人が他のどんな動物にも勝るところは理性 があることです。理性が耐えることを学び、他者への感謝や謙譲を学び、良い人間関係をつくり、住み良い社会をつくります。その理性は生まれながら備えられているものではなく、教育によって培われるものです。生まれたての赤ちゃんは、自分が世の中心にいるものととらえています。やがて親の教えと経験によって理性が芽生え、他者との円滑な関わり方を学んでいきます。理性は人が人間としてより高度な暮らしを創造するのに不可欠な要素です。
しかし、強い理性を培うことは容易ではありません。子どもに適切な教育を課さなければ、欲望のみが肥大し、喧嘩や争いの絶えない弱肉強食の醜い社会になってしまいます。子どもたちにより強い理性を培うこと、これが義務教育・公教育に課せられた責務です。
教育基本法では、第6条に「教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めること を重視する」と明記され、第10条に「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣 を身に付けさせる」とあります。どうか、この法に則り、学校のすべきこと、家庭のすべきことをよくご理解いただき、協力して教育活動を進めていきましょう。
中学校は義務教育の出口でもあります。将来の社会を支えていく担い手として、ふさわしい学力と社会性を身につけなければならない場でもあります。当然、厳しさも要求されます。小学校7年生という感覚でなく、中学校1年生として、気を引き締めて4月を迎えられますよう、今からその心構えなどご指導をお願いします。
鷹来中学校は、学校・家庭・地域の連携によって、子どもたちの、義務教育における学習内容を保障できるような学校でありたいと考えます。そのために、職員は全力を尽くします。どうか、ご家庭の方でも、この方針にご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
-
道徳の研究授業から
- 公開日
- 2010/02/08
- 更新日
- 2010/02/08
校長室から
コミュニケーション能力
先週、1年生で道徳の研究授業を行いました。適切な言動について考えさせる「アスカの決断」という情報モラル関連の話を資料として使用しました。携帯電話やメールは自分の目の前に伝える相手がいません。その相手の表情や反応も見ないで、一方的にこちらの伝えたいことだけを伝えることになりがちです。そんなメールによる友人間のトラブルを扱った内容です。
この授業を参観して、以下のような感想を持ちました。
コミュニケーションツールとしての携帯電話の是非や、その使い方を考えることも大切です。しかし、本質的な問題は基本となるコミュニケーション能力をどう育成するのかにあるのかもしれません。
社会生活にもっとも必要なコミュニケーション能力は、端的にいえば、自分の内面を外に発信する力と他者の発信を受信する力。基本的には義務教育9年間の国語で培う「表現力」と「理解力」を意味します。コミュニケーションは双方向、自分と他者との相互交流が原則です。最終的には、自分の言葉で自分の思いを伝える力を身につけ、その力によって他者と関わり合い、望ましい人間関係をつくることが重要です。さらに、他者を認め、自分を認めることで、自制心や自立心、ストレスへの対応能力などを身につけることにまでつなげる必要があります。
また、丁寧な言葉で話をすることも大切なことだと思います。感情もあらわに、思ったことをそのまま相手にぶつけることを避ける効果が期待できます。そのまま思いをぶつけると、両者が感情的対立に陥ることが考えられます。丁寧な言葉で話すためには、一度自分の頭の中で話す内容を整理しなければならないため、落ち着いて自分の主張や考えを表すという習慣が身につきます。すぐに「キレる」子どもたちの多くは「表現力」と「理解力」の育成が十分でないのかもしれません。
私たち教師は、国語やその他の教科指導が道徳や心の育成にも大きく関与することを意識して、意図的に授業を行わなければならないと思っています。 -
小中交流活動「大手のつどい」
- 公開日
- 2010/02/08
- 更新日
- 2010/02/08
校長室から
☆大手のつどい☆
2月6日(土)大手小学校の体育館で行われた「大手のつどい」(音楽集会)に本校の吹奏楽部の5人がゲスト出演してくれました。サックス5重奏を披露し、参加した全校児童や保護者の方から大きな拍手をいただきました。
小学生と中学生の交流のきっかけにという大手小学校の安藤校長先生の発案で、今回の交流が実現しました。これからも鷹来中ブロックの小中学校4校は連携して、地域の皆さんにご支援・ご協力いただきながら、児童生徒の健全育成を推進していきたいと思います。よろしくお願いします。 -
職場体験学習
- 公開日
- 2010/01/26
- 更新日
- 2010/01/26
校長室から
先週の1年生の職場見学に続き、今週は2年生が職場体験を行っています。
職場体験学習は、生徒が働いている多くの人と直接かかわることで、異世代とのコミュニケーション能力を高めるとともに、社会人としての基本的マナーや言葉遣いなどを身につけることができる場でもあります。これを契機に、生徒が地域の産業に興味を持ち、地域に対する誇りや愛着を持って、地域での生活を送ってくれることを強く願っています。
この「職場体験学習」の意義をご理解いただき、快く職場を提供してくださった各事業所の皆様には、心より感謝申し上げます。今後とも、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
何のために働くのかと問われると、「お金のため(経済活動)」もしくは「理想のため(自己実現)」と答える人は多いかと思います。しかし、もう一つ「社会のため(役割分担)」という考え方もあります。私たちが社会生活を送る上で、否応なしに「だれかがやらなければいけない仕事」というものがあります。それを様々な人が分担していくのも大事なことなのです。「役割分担」という視点で仕事を見れば、どんな仕事にでも必ず大きな意味があります。
「働く」とは「傍(はた)楽(らく)」、つまり「傍=周り」を「楽にする」という意味が語源だという説もあるそうです。働くということは、自分のためではあるけれど、自分のためだけではないということも忘れてはならないと思います。
-
平成21年度 三学期始業式
- 公開日
- 2010/01/07
- 更新日
- 2010/01/07
校長室から
早朝から霙(みぞれ)まじりの雪も降り、たいへん冷え込んだ中で始業式を迎えました。
三学期は一年の締めくくりの大切な時期です。これからますます寒くなりますので、保護者の皆様におかれましては、お子さんの体調管理には十分留意してください。
★三学期始業式 式辞
あけましておめでとうございます。いよいよ三学期、各学年のしめくくりの大切な学期です。かけがえのない自分という存在を大切にしながら、充実した時間を過ごしましょう。そのためにもくどいようですが、「命」「心」「未来」 の3つのキーワードについてここで再度確認したいと思います。
一つ目「いのち」、命は、一人に一つだけしかありません。なくしてしまえば代わりはありません。自分の命も人の命も、どちらも大切にできる人になってください。特に、卒業、新たなる進路を目指す三年生のみなさんは、自己の体調管理をしっかりして、生活のリズムを整えましょう。
二つ目「こころ」は、よく考えて行動し、心の力をつけようということです。難しいことではありません。例えば、進んであいさつをするとか、友だちに親切にするとか、「ありがとう」や「ごめんなさい」 を素直に言えるようにすること。ちょっとしたことで、私たちの心はさわやかになり強くなれるのです。人の嫌がることをしない、されたら嫌だときちんと言う、誰かがされているところをみたら助けてあげる。
三つ目「みらい」は、自分のかがやく未来に向かって、命と心を大切にして、さらに、しっかり学習して力をつけようということです。
各学年のゴールは、次の学年、次の進路、新たなステップへのスタートラインでもあります。しっかりと自分の力を各学年のレベルまで到達させ、ゴールインしてから、スタートラインに立ちましょう。
ますます寒くなりますが、健康に気をつけて、充実した三学期にしましょう。これで始業式のお話を終わります。 -
第二学期終業式 式辞
- 公開日
- 2009/12/22
- 更新日
- 2009/12/22
校長室から
2009年もあとわずか。二学期の終業式というよりも、みなさんにとっては冬休みの始まりというイメージでしょうか。
さて、二学期の自分の学校生活を振り返ってみてください。どんなことが思い浮かびますか。行事の多い二学期でしたが、新型インフルエンザの流行によって、いろいろ大変でした。体育大会までは無事に行えましたが、新人戦の直前まで学級・学年閉鎖もあって練習も満足にできないまま、大会に臨み、その力を十分に発揮できなかったのは残念でした。文化祭でも合唱コンクールに向けて練習を進めていく中で、なかなか全員そろって練習することができませんでした。福祉体験など中止になった行事もありました。しかし、これからの人生においても、すべてが計画通り順風満帆に進んでいくものではありません。そういう困難な局面にぶつかったとき、柔軟に対応していくことは重要なことです。大切なことは、あきらめることではなく、今できることは何かを考え、目標を修正し、再びチャレンジすることです。新型インフルエンザに翻弄されたこの二学期をいい教訓にしてください。
さて、年が明ければ三年生はいよいよ義務教育9年間の集大成でもある進路決定のときを迎えます。健康第一、体調管理をしっかりして、入学試験や就職試験にチャレンジできるようにしてください。
まもなくやってくる未来、2010年がみなさんにとって、よりよい成長をもたらす年になることを祈っています。
話は変わりますが、先週、消防署の方が学校にみえました。本校の一年の生徒が、よい行いをしたので褒めてほしいという依頼でした。少し前の話ですが、7月25日に、町屋町で作業所の資材に火がつけられ、ボヤになっていたところを、○○くんとお父さんが消火に協力し、消防車が到着する前に火を消し止め、本格的な火災になるのを防いでくれたそうです。○○くん、ありがとう。
これからもこのようないい話を地域から聞かせてもらいたいと思います。鷹来中の生徒の評判がますますよくなるように、叱られるのではなく褒められる機会が増えるように、みなさんも心がけてください。
-
吹奏楽部演奏会を終えて
- 公開日
- 2009/12/18
- 更新日
- 2009/12/18
校長室から
日ごろお世話になっている地域の皆さんに、自分たちの演奏を通して、音楽のすばらしさや楽しさを伝えたいという部員の熱い思いから始まったこの演奏会は、8年も続いています。他に例を見ないすばらしい行事だと思います。部員の日々の努力に加え、保護者の皆さんのご理解とご協力、そしてこの地域の皆さんのお支えがあってこそ、このように継続開催できるのだと思います。この鷹来中校区だからできる行事だと思います。
今回の演奏会も小さなお子さんからお年寄りの方まで、幅広い年齢層の方々に楽しんでいただけるように、演奏曲目や演出にもさまざまな工夫がなされていました。この会場に集まったすべての方が、すばらしい時間を共有することができたと思います。
本演奏会の開催にあたり、吹奏楽部保護者会の方々、OBの方々をはじめ種々のお世話をいただいた皆様、ありがとうございました。特に、保護者の方には、楽器や資材の運搬、会場設営といった事前の準備から、当日の会場整理、駐車場・駐輪場の案内や整理、会場の後片付けなどにご協力いただき、心から感謝しております。このようなすばらしい行事を、これからも続けていくために、学校側もいろいろと努力していきたいと思います。
また、本校では、その他の部活動についても吹奏楽部に負けず劣らず、各顧問は情熱と愛情を持って指導にあたっています。保護者の皆さん、ご支援をよろしくお願いします。
校長 伊藤 孝之
-
生徒指導上の諸問題に関する調査結果から
- 公開日
- 2009/12/01
- 更新日
- 2009/12/01
校長室から
11月30日、文部科学省から平成20年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(暴力行為、いじめ等)が公表されました。新聞等でも報道されたので、ご存知の方も多いと思います。中でも、中学生の暴力行為は過去最高の4万件を超えた そうです。先月、沖縄県うるま市で中学校の同級生らによる暴行事件が相次ぎ、14歳の男子生徒が死亡、女子生徒が重傷を負った事件もありました。
文部科学省は、都道府県教委の分析として「自己の感情抑制ができない」「規範意識の低下」「家庭の教育力の低下」 などを増加理由に挙げています。また、暴力の背景には、日常的に子どもたちが親しんでいるメディア(インターネットやマンガ、テレビのバラエティ番組など)の言語表現が荒れ、感情や感覚の直接的な表現が主流 になっていることもあげられると思います。その影響を受けた子どもたちは深い思考や、自分の感情をいったん受け止めてから表現するということが苦手になります。したがって、自分の感情を抑えられないまま、教師や仲間と対立したときに、自分を抑えて引くという行為ができず、つい手を出すという状況となります。
善悪の判断を体得すべき時期である小学校低学年のころまでに、大人に厳しく叱られるという経験が少ないままで、中学生になった子どももいるのかもしれません。やはり、小さいうちに家庭で「あいさつ」「場に応じた正しい言葉遣い」「他人に迷惑をかけない」などのごく基本的な生活習慣を体得させ、地域や学校という社会で、他者と関わり合いを通して、それを確認しながら、身につけていくということが大切だと思います。
暴力行為だけではなく、問題行動を起こす子どもたちの背景は複雑です。家庭と地域と学校が連携 して教育に当たることが必要だと、改めて強く感じました。
-
第2回進路説明会
- 公開日
- 2009/11/20
- 更新日
- 2009/11/20
校長室から
新型インフルエンザの流行のため学年閉鎖となり、説明会が本日に延期になりました。朝晩の冷え込みも厳しくなり、暦の上では霜月もう冬です。中学3年の冬は進路選択という試練の季節でもあります。今後は季節性のものも含め、大切な入試の日・就職試験の日など、感染することのないように、予防に努めてください。
第1回目の説明会では、自己責任ということに絞って話をしました。その話を真剣にとらえてくれた人は、努力の姿勢を見せ、自分の未来に向かっていろいろ考えているようです。なかなかその意味をとらえ切れなかった人は、目前の選択に対して甘い考えしか持っていないようです。繰り返しますが、学校は全員の進路を応援するつもりです。しかし、進路を決めるのは自分だし、自分で努力しない子は応援の仕様がない。今からでも遅くはありません。未来に向かって努力する気になってください。
シドニーオリンピック女子マラソンで金メダルを獲った高橋尚子選手は「あきらめなければ夢はかなう」とか「強く願うことが大切」という言葉をよく話しています。それはとても大切なことだと思います。ただし、ただ強く願う、ただあきらめないだけで夢は実現しません。それにふさわしい努力を重ねること、目標に向かって忍耐強く取り組み続けることが必要です。自分の目指す夢に向かっての第一歩となるのが、この進路選択です。学力を充実させ、規律正しい生活を送る努力を続けてください。「冬来たりなば、春遠からじ」ということばがあります。希望の春を迎えられるように、この冬に頭と心と体をしっかり鍛えてください。
さて、保護者の皆さん、現在はどこの中学校でも、多くの生徒が進学を希望し、また希望したほとんどの生徒は高校・専門専修学校へと進むことができます。昔は中学校の3年間が大人社会への準備期間といわれていましたが、近年は高校3年間がその期間といわれ、自立のための3年間とも表現されています。その重要な3年間をどこでどう過ごさせるのか。自立のために必要な 学力・生活力・社会力 をきちんとつけるためには、どんな進路選択が必要かをよく話し合って検討してください。
学力については、さらに高度な学習を希望し大学進学をめざすのか、最低限高校卒業の資格がほしいのかによっても、大きく違ってきます。生活力は、主に家庭の教育力が大きいと思いますが、調理、洗濯、掃除など身の回りのことを自分でやっていく力、また1ケ月間の生活費を決められた金額でやりくりするような力です。社会力は、新しい環境で、いい人間関係をつくるために、エチケット、マナー、最低限の身だしなみということがきちんと理解できるかどうかという力です。これからの3年間で3つの力をしっかりとお子さんに身につけさせ、社会的に自立させるためにはどのような進路先がふさわしいのかということも視野に入れてご検討ください。
具体的な話は、進路担当の係からあると思いますが、担任やお子さんとの意思の疎通を十分に図りながら、いよいよ目前に迫った進路選択に取り組んでください。
-
創作部の敬老会ボランティア
- 公開日
- 2009/09/24
- 更新日
- 2009/09/24
校長室から
以前に「中学生と地域との交流」 として紹介した、創作部の敬老会の呈茶ボランティアの報告です。
9月21日敬老の日に、桃山地区の敬老会がグレイスフルで行われました。その席に、本校を代表して創作部の中から5人がボランティアとして参加させていただきました。前日のいけばなの指導までしていただき、生徒にとってはとても充実した体験ができたと思います。式典会場でも鷹来中の生徒がボランティア参加していることを紹介いただき、地域の方にも交流活動を知っていただくよい機会となりました。桃山区長様をはじめ、協力くださった地域の方々に深く感謝いたします。
※写真は、当日会場に展示していただいた創作部員のいけばなの作品です。 -
吹奏楽部への感謝状
- 公開日
- 2009/09/24
- 更新日
- 2009/09/24
校長室から
連休最終日の9月23日、春日井市総合福祉センターで「献眼・献腎顕彰式典」が開催されました。毎年開催されるこの式典では、この8年間、本校の吹奏楽部が演奏を披露しています。
8年間の吹奏楽部の活動に対し、主催者の春日井中央ライオンズクラブから、感謝状をいただきました。校長として、長年このような活動を続けてきた本校の吹奏楽部を誇りたい気持ちで一杯です。
校区外ではありますが、これもある意味地域へのボランティア活動といえると思います。生徒たちはこういう活動を通じて、多くのことを学ぶことができると思います。これからも、中学生が地域の一員として活動できる場面を探して、チャレンジさせていきたいと思います。
-
9月 PTA全委員会にて
- 公開日
- 2009/09/10
- 更新日
- 2009/09/10
校長室から
PTA全委員会 学校長あいさつ 9月9日(水)
こんにちは、まだまだ残暑厳しい中、お集まりいただきありがとうございます。
いよいよ、2学期が始まりました。学問の秋、スポーツの秋、芸術の秋と様々な取り組みに最適の季節だと思います。体育大会、部活合同練習会、文化祭と行事も目白押しですし、3年生はいよいよ進路選択の大事な時期です。
さて、夏休み中はホームページ等でも紹介しましたが、部活動の大会・発表会が行われ、生徒も顧問も十分に力を発揮して、近年にない結果(成績という意味ではなく、それぞれ心に残るような経験をしたことも含めて)を残せたと思います。努力して打ち込めば、それなりの成果は出せる 、ということが証明されたと思います。男子バスケ、女子ソフトテニスが準優勝、女子バレーが3位と健闘しました。その他の部活もよいチームに成長してきました。文科系の部につきましても、運動部に負けず、それぞれの特性を生かした活動に励んでいます。これも、サポートしていただいている保護者の皆様のおかげだ と思います。ありがとうございました。ただ、生徒の努力はもちろんですが、それに加え、早朝から夕刻まで、あるいは休日も厭わずに指導に当たっている顧問の情熱 の表れでもあることも評価していただきたいと思います。
さて、昨年度から児童生徒の健全な育成を目指して、地域との連携や校区内の小学校との連携を進めております。オープンスクールの際の交流、9月1日始業式に実施した小中4校の一斉下校での見守り、声かけの活動など、PTAの方だけでなく、多くの地域住民の方にも協力いただき、少しずつ成果が挙がってきたと思います。敬老の日のイベントにも、桃山区のご好意で本校の創作部員を中心にボランティア参加させていただくことになりました。生徒が地域でその存在をアピールするよい機会だと思いますので、今後もこういう形での交流を模索していきたいと思います。
最後に、皆様方にご心配いただいている生徒指導面ですが、きちんと学習意欲を持ち規律を守って生活している生徒がほとんど ですが、なかなか落ち着いた生活ができない生徒がどの学年にも数名おります。規範意識が低く、ガマンすることが苦手で、自分勝手な行動が多い、そんな生徒たちの指導については、学校だけではなかなか難しい面もあります。家庭と連携を取りながら指導にあたるわけですが、なかなか改善されません。保護者の方が放任しているというわけではなく、わが子でありながらどう対応すべきか迷っているという状況もあります。そこで、学校と家庭というタテの連携だけでなく、保護者同士や地域と家庭というヨコのつながりも必要 だ思います。さらには、小学生の段階での指導についても、先を見越した指導が必要とされてきます。ですから、地域連携、小中連携を図りながら、地域ぐるみで児童生徒を育てていくという意識が大切だと主張しているわけです。個々の家庭で考え方が違うのは当然ですし、価値観も違います。しかし、公教育の小中学校では学力と共に社会性 を身につけることも大切です。個性を尊重することも大切ですが、ある程度周りを理解し、周りと協調しながら生活 していくことを学ぶことも必要だと思います。そのためにも、地域に協力いただきながら、地域の小中学校とその保護者の皆様が互いに信頼 し合うことが大切です。その原動力になるのが、PTAの委員の皆様だと思います。今後とも、よろしくお願いします。
-
中学生と地域との交流
- 公開日
- 2009/09/01
- 更新日
- 2009/09/01
校長室から
「地域の中学校」を目指して、昨年度から様々な取り組みをしてまいりました。
地域の皆様のご協力のおかげで、少しずつですが交流が図れてきたように感じています。昨年度は、地域の方に実際の中学校を知ってもらうために、来校いただく機会を増やすことからはじめました。今年度は、職場見学や職場体験以外にも、生徒が地域へ出て行って交流を深める機会を模索しています。
もともと数年前から、鷹来中にはすばらしい地域交流のイベントがあります。生徒と保護者と地域の方が一体となって作り上げている、吹奏楽部の地域演奏会 です。もちろん本年度も、開催を予定しています。
ただ、大きな行事とは別に、生徒が自然に無理なくかかわれるものという前提で、地域の方と相談しながら交流活動計画を考えています。郷土に伝わる伝統文化、地域ボランティア、ジュニア防災組織・・・いろいろなアイデアを現在検討しています。
そんな中、現在具体的に計画されていることを紹介します。
本校の創作部 は、本年度から文化や芸術についての探求を軸に据え、日本の伝統文化である茶道を体験したり、中学校文化連盟の美術展に参加するなど積極的に活動しています。その創作部の部員が、ボランティアとして、桃山地区で行われる敬老会の呈茶を手伝うことになりました。よく本校に訪問いただいている健全育成関係のボランティアの方が、地元で茶華道教室を開いてみえます。その方が、このアイデアを提供してくださいました。夏休み中の8月23日には、この茶華道教室の浴衣の茶会 にも部員を招待してくださいました。(※写真はそのときのものです。)また、敬老会の前日には、生け花 の指導もしていただき、当日の会場に生徒の生け花作品も展示してくださる予定だそうです。参加生徒は少数ですが、まず具体的に活動することに意味があると考えます。桃山区長様をはじめ、地域の方々に感謝いたします。
今後もいろいろと地域交流についてご理解・ご協力、そしてご助言くださいますようお願いします。
-
2学期がはじまりました
- 公開日
- 2009/09/01
- 更新日
- 2009/09/01
校長室から
いよいよ2学期が始まりました。
始業式で生徒を前に、次のような話をしました。
始業式 校長式辞
それぞれの充実した夏休みが終わり、今日から、二学期が始まります。夏休み中には、各種大会や発表会などに学校代表として多くの皆さんが参加し、それぞれ成果をあげてくれました。また、それが終わって次の目標に向けて一・二年生を中心として、暑い中、一生懸命部活動の練習に参加した人も多かったと思います。そのほかにも、三年生の人たちは、自分の進路を考え、学習面でも多くの人が努力したことだと思います。常に目標を持って努力することはとても大切なことです。こういう経験はこれから先のあなたたちの人生にとってとても意味のあることです。
さて二学期は落ち着いて学習に専念する時期であると同時に、体育大会、部活合同練習会、文化祭などの行事もあります。これらの行事は、クラスや部活の仲間、学年を超えた全校の仲間で協力しないとできないことばかりです。一学期よりもさらに充実した学校生活が送れるように全力を尽くしましょう 。
さて、もうひとつ、重要な話をします。昨年度から、本校は校区内の小学校や地域と連携を深めてきました。地域の方は生活の基盤である自分たちの地域をよりよくしていきたい、という共通の思いをもっています。そのためには現状をよくすると共に、未来の地域社会を支える子どもたちを健全に育てることが大切だと考えています。そのために鷹来中校区生活指導連絡協議会という学校と地域と家庭が協力する組織を作って活動しています。その取り組みの一つとして、本日、本校と鷹来小・大手小・西山小が安心安全ふれあい下校を実施します。地域のボランティアの方々に協力いただき、下校に付き添っていただいたり、下校の様子を見守ってもらったりします。その際、地域の方には児童生徒に声をかけていただくようにお願いしてありますので、地域の人に出会ったら、きちんとあいさつをしてください。以上で話を終わります。
保護者の皆様、地域の皆様、今学期も 「みんなの楽校」鷹来中学校 をご支援くださいますよう、よろしくお願いします。
-
夏の大会・発表会
- 公開日
- 2009/07/30
- 更新日
- 2009/07/30
校長室から
夏の市大会・発表会が終わりました。満足する結果が残せた部と思うように力を発揮できなかった部があったと思いますが、全体的にはよく努力し、それぞれが成果を残せたと思います。特に運動部で団体種目 準優勝2チーム、3位1チームという結果は立派だと思います。生徒たちの努力に加え、顧問の先生方の情熱のある指導や保護者の方々の理解と協力の賜物だと思います。ご苦労様でした。
7/30 出校日の校長講話
暑い中、春日井市の大会・発表会が終わりました。私も学校代表の皆さんの応援に各会場へ足を運びましたので、今日はその感想をいくつか紹介します。
野球部の試合は、雨で延びたために、教頭先生に応援を頼みました。順延となり、やや気合をそがれたのか、押していながらもあと一押しができず、惜敗したとききました。残念です。
サッカー部 1回戦途中から応援しました。後半交代してすぐにFWの選手が追加点となるシュートをあざやかに決めたシーンが印象に残りました。グランドの状態がよくない中、体を張って懸命に守るDFやGKの姿も強く印象に残りました。
男子バスケット部 鷹来中が会場ということもあって、多くの応援の中、蒸し暑い体育館の中をよく走り抜きました。期待にこたえて、立派に準優勝を勝ち取りました。愛日大会でも強豪チーム相手に健闘し、見事3位に入賞しました。
ハンドボール部 相手のデフェンスを破れず、なかなか得点できませんでしたが、最後に果敢に攻撃をしかけ、連続してシュートを決めたシーンが印象に残りました。部員数が少なくて、3年が引退した昨年夏以降なかなか十分な練習ができなかったことを考えると、よくがんばったと思います。部員数も増え、これから先が楽しみだと思います。
女子ソフトテニス部 団体戦を応援しました。力強いサーブと安定したショットで、強さを感じました。決勝では、あと1ポイントで優勝というところまで漕ぎ着けたのですが、惜しくも敗れました。しかし、りっぱな準優勝でした。団体戦で勝つということは本当に価値が高いと思います。愛日大会では強豪チーム相手によく健闘しました。
卓球部 個人戦を応援しました。あと1ポイント、勝利目前で緊張からか、ミスをする選手もいました。個人戦の難しいところだと思いました。しかし3名ほどは初戦を突破したので、これから先が楽しみだと思います。
男女バドミントン部 団体戦を見ました。参加校も増え、レベルも高くなってきたので、予選リーグから接戦が多くなってきたように思いました。毎大会鷹来中が上位に入るのは、当たり前のことではなく、伝統を受け継ぎ、部員のみなさんが日々着実に努力を重ねてきた結果なんだと感じました。男子は今日も県大会に出場しています。
剣道部 応援に行きましたが、なかなか試合時間が合わずに残念でした。個人戦では何勝かできる選手も出てきたようです。1・2年生の選手もいたので、次の大会が楽しみです。
女子バレー部 予選リーグでは、なかなか思うように力を出せなかったようですが、決勝トーナメント1回戦で、1セット先取されながらも、自分たちのバレーを貫き、逆転しました。最後は立派に3位を勝ち取りました。
女子バスケ部 1回戦第4クウォーターから、応援しました。ワンゴール差の攻防で、まさに最後の1秒まで気の抜けない展開でした。ワンゴールリードのまま、試合終了のホイッスルを聞いて、選手もベンチの部員も感動して泣いていたようです。部員が一丸となって、全力でこの一勝に賭けていたという様子が伝わってきました。
吹奏楽部 発表会は、聴く側の観客を圧倒する迫力がありました。周りの評判もよかったようです。東尾張コンクールでは結果は銀賞でしたが、最高の演奏ができたと思います。
演劇部 舞台発表は残念ながら観ることができませんでしたが、創作部の協力を得ながら、少ない人数でもよく工夫努力を重ねたりっぱな舞台だったそうです。文化祭での発表を楽しみにしています。
創作部 今年は、いろいろなことにチャレンジしているようです。文化フォーラムの市内中学校の合同美術展にも力作の絵手紙などを出品しました。
英語のスピーチコンテスト ちょっぴり緊張気味でしたが、堂々とスピーチできたと思います。作文の部では最優秀を獲得しました。
その他、水泳など個人で出場し、よい成績を収めた生徒もいました。
どの選手も今もてる力を出し、全力を尽くせたと 思います。それぞれが、次の新しい目標に向かって、また全力を尽くしてください。感動は言葉では伝えにくいものですが、私の感動を少しでもみなさんに伝えたいと思い、今日はこんな話をしました。