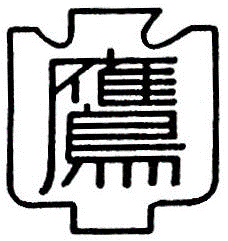-
修了式
- 公開日
- 2009/03/25
- 更新日
- 2009/03/25
校長室より
3月24日に修了式を終え、春休み(学年末の休業)を迎えました。保護者の皆さん、地域の皆さんのご理解・ご支援のおかげで、今年度も円滑な学校運営ができました。心より感謝申し上げます。
次年度も「地域の学校」として、子どもたちが生き生きと学べる学校、保護者の方が安心して送り出せる学校、地域の方が愛着を持てる学校を目指して、職員一同努力しますので、よろしくご支援ください。
修了式 式辞
おはようございます。今日は学年の締めくくり、修了式です。まず、今日までの一年間のことを振り返ってください。そして、次の一年をどう過ごすかを考えてください。
有名な中国の古典、儒教の基本テキストである五経の筆頭に挙げられる経典 易経(えききょう)という書の中に、
「君子は豹変す」 「小人(しょうじん)は面(おもて)を革(あらた)む」 と言う言葉があります。
豹の毛が季節に合わせて抜け変わり、美しい斑文となることから、君子つまり立派な人は、たとえ過ちを犯しても素早く善に立ち戻れるとか、君子は、時代の変化に合わせて自分を素早く的確に変えていけるとの意味です。現代風に捉えれば、「誤りに気づいたら、素早く今までの意見を改めたり、行動のパターンを転換してよい」 という意味です。
「君子は豹変す」の後の「小人(しょうじん)は面(おもて)を革(あらた)む」小人つまり、たいしたことのない人間は、変われるが、それは「表面的なもの」にとどまるという意味です。
確かに、私たちは過去のあやまちや自分のこだわりに引っ張られて意識や態度、生き方をすぐに変えられないものです。「こうありたい」「ああなりたい」と思いながらも、結局同じような毎日を過ごしてしまっている。では、そんな自分を大きく変えるにはどうすればいいのか。それには、大きな環境の変化を利用するのが一番効果的だといわれています。つまり、学年が一つ進級し、クラスも変わるこの時期こそが、最も自分を変えられる時期だということになります。義務教育を終えて、自ら進路を選択時期がまた一歩近づいてきます。今のままの生活態度でよいのか、選択の幅を広げるためにも、社会で通用する人間となるためにも、この機会に自分を見直し、よりよい自分を目指してください。
「チェンジ」と言う言葉が流行しました。日本語で言えば「豹変」です。自分の中での自己変革です。これができる人間になってください。
4月7日の始業式にはいい方向に豹変した姿を見せてください。
-
卒業式の式辞
- 公開日
- 2009/03/09
- 更新日
- 2009/03/09
校長室より
3月6日、第34回鷹来中学校卒業証書授与式を挙行しました。
多くのご来賓、保護者の皆様には、雨の中、卒業生の門出を祝っていただきありがとうございました。
当日の校長の式辞を掲載します。
式辞
春雨や蓬(よもぎ)をのばす艸(くさ)の道 この芭蕉の句に詠まれたような、草木を育む縁起のよい恵みの雨のこのよき日、平成二十年度卒業証書授与式を迎えることができました。
本日は、ご多用の中、ご来賓の皆様には、早朝よりご臨席いただきまして誠にありがとうございます。高いところからではありますが、お礼申し上げます。
さて、卒業証書を授与された百七十四名の卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。今、あなた方一人一人に卒業証書を手渡しました。その一枚の紙の中には実に様々なものが宿されています。小学校から通算しての義務教育九年間。その長い年月、元気に登校し、基礎・基本の学習を身につけた皆さんの努力 。それを絶えず見守り、世話をしてくださったご両親の愛情 。そして皆さんの成長のために、ある時は厳しく、ある時は優しく導いてくださった先生方の情熱 、安全に登下校できるようにと見守ってくれた地域の皆様方の思い 、そして楽しい学校生活ができるようにと気遣ってくれた教育委員会のご配慮 など。多くの人達の陰のご苦労の積み重ねによってはじめて手にすることができた卒業証書なのです。感謝の気持ち を忘れないでください。
皆さんは、この一年間、最高学年としてリーダーシップを発揮し、在校生のよき手本となりました。また、学校の顔として対外行事にも出場し、活躍してくれました。その活動ぶりは、在校生にしっかりと受け継がれて行くことでしょう。
卒業の門出に当たり、ひとつお話をします。
「おもしろき こともなき世を おもしろく 住みなすものは 心なりけり 」
これは幕末の動乱期に奇兵隊を考案し、活躍した長州藩士 高杉晋作が自分の人生を振り返って詠んだ歌だと言われています。この歌の意味は、ちっとも面白いことがないと思われる世の中でも、自分の心のありようで面白く感じ、楽しく過ごせるものだ。つまり、同じ体験をしても、その心の持ちよう で、感じ方が違ってくるということです。
例えば、想像してください。真夏の運動場や体育館で、汗をかいて部活動の練習をしています。のどはカラカラ、やっと休憩時間です。水筒を見るとお茶は半分残っています。そこで、その水筒を見てどう思いますか。「もう半分しかない」と思いますか、「まだ半分もある」と思いますか。「半分しかない」と思うと心が不安になってきます。これはマイナス思考です。マイナス思考は、物事をする前に結果にこだわり過ぎて、感じなくてもよいプレッシャーを自分にかけてしまうため、実力を発揮できず、よい結果が得られません。逆に、「まだ半分もある」と思うと、心は落ち着き、安心します。これがプラス思考です。
プラス思考とマイナス思考の違いがわかりますか。プラス思考の場合、前向きな考え方ができるので、困難な場面では、不安をかかえるマイナス思考の場合よりも、圧倒的によい結果が得られます。
心配性の人でも、自分に自信が持てない人でも、自分をプラス思考にすることは難しいことではありません。どんな場合でも「よい」面を探す努力をすること。どんな人にも必ずよい点がある、そう信じること。そして、自分を見つめ、自分のよい点を発見しましょう。必ずよい点はあります。自分の中でここがよいと思うところを見つけてください。
それから、どんなに小さな出来事にでも感謝の思いを持ち続けること、そうすると心が落ち着いて、不安な気持ちは消えていきます。このプラス思考を取り入れて、これからの長い人生を明るく楽しく、前向きに生きてください。
「おもしろき こともなき世を おもしろく 住みなすものは 心なりけり 」
この言葉を餞(はなむけ)に贈ります。
これからも、命 を大切にし、心 を成長させながら、輝かしい自分の未来 に向かって、全力を尽くし 、力強く進んでください。
さて、在校生の皆さん。皆さんは、先輩が築いてくださった輝かしい伝統とよき校風をしっかりと受け継ぎ、さらに発展させるよう、プラス思考で前向きに努力してください。
最後になりましたが、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。たくましく成長されたお子様の晴れ姿をご覧になり、さぞお喜びのことと拝察申し上げます。今日まで学校にお寄せいただきました温かいご支援ご協力に対しまして、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
以上、卒業生の皆さんの限りない前途を祝し、式辞といたします。
平成二十一年三月六日 春日井市立鷹来中学校長 伊藤 孝之
-
PTA全委員会
- 公開日
- 2009/02/16
- 更新日
- 2009/02/16
校長室より
2/14(土)春を感じさせる陽気の中、本年度最後のPTA全委員会が行われました。
会長の鶴巣さんのあいさつの中にも「委員はたいへんかもしれませんが、その中で、得るものも多い」というプラス思考の言葉もありました。本校のPTA会長に加え、市のPTA連絡協議会の副会長の要職もお務めいただき、たいへんご苦労様でした。また、委員のみなさんには、あらゆる機会に学校を支援いただき、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
※ 校長あいさつを掲載します↓
本年度最後の全委員会となりました。本校の教育活動も皆様のお力添えにより、円滑に推進することができたと思います。今後、役員・委員という立場を離れましても、学校教育活動ならびにPTA活動をご支援くださいますようお願いします。鷹来中はこの地域の公立学校であり、この地域の子どもが安心して通え、この地域の住人が自慢できるような学校でなければならないと思います。地域のみなさんの協力を得て、よりよい学校にするためにも、どうか今後も中学校に関心を寄せていただくとともに、ご支援をよろしくお願いします。
さて、保護者の方に、基本的生活習慣の中で最も重要な「あいさつ」についてのお願いをします。「おはよう」「さよなら」「ありがとう」「ごめんなさい」これらの言葉が素直にいえる人間は周りから受け入れられやすいと思います。あいさつの言葉は周りの空気を和ませる力を持っています。確実に身につけなければならない「生きる力」として、基礎・基本的な学力と同じくらい大切なものです。あいさつは、家庭で培い、学校で試しながら、社会に出る前にきちんと身につけていくべきものだと思います。どうか、今後とも、その習慣づけをよろしくお願いします。
-
校長室の生花
- 公開日
- 2009/02/13
- 更新日
- 2009/02/13
校長室より
校長室のドアを開けると、さりげなく活けられた 美しい花 が目に止まります。この花は用務員の安藤さんが、いつも活けてくれています。
およそ花など似つかわしくない私でも、このように 美しい花 を見ると、朝から すがすがしい 気分、穏やかな気分になれます。
同じように、生徒の皆さんが、毎朝、校門を入るときに、すがすがしい 気分になれる方法はないでしょうか・・・
門のあたりで、仲間や先生、安全指導の保護者の方などに会って、おはよう とあいさつを交わすことで、そんな気分になれたらいいなと思います。
-
2月集会講話
- 公開日
- 2009/02/10
- 更新日
- 2009/02/10
校長室より
今朝の朝練習の様子です。 ↑
寒さに負けず、熱心に練習に取り組んでいます。
多くの鷹中生は意欲的に学校生活を送っています。
昨日は、全校生徒が運動場で集う、最後の朝の集会でした。
そこで、話した内容をここに掲載します。
3年生は私学の推薦入試や一般入試を終え、理想的な結果を手にした人、残念ながら思うような結果ではなかった人、いろいろだと思います。
このあと公立の入試を控えて、少し緊張気味の人も多いかと思います。健康に注意して、まだまだできることはあるはずですから、全力を尽くせるよう努力してください。
さて、受験、この結果が未来のすべてではなく、まず第一歩にすぎません。
みなさんの未来はまだまだうんと先まで続くのです。
世界史に出てくるイギリスのウィンストン・チャーチルという人を知っていますか。彼は第二次世界大戦の困難な時期に強い意志と 楽観主義者をもって、憔悴したイギリス国民を激励し、イギリスを復興に導いた政治家です。そのチャーチルの言葉をみなさんに贈ります。
悲観主義者 はすべての好機 の中に 困難 をみつけるが、
楽観主義者はすべての 困難 の中に好機 を見いだす。
心の持ちようで、人生は楽しくなります。
-
3学期が始まりました
- 公開日
- 2009/01/07
- 更新日
- 2009/01/07
校長室より
明けましておめでとうございます。
本年も鷹来中学校の教育活動推進に、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
始業式での校長式辞を紹介させていただきます。
三学期始業式 式辞
あけましておめでとうございます。始業式にあたって、みなさんにお話したいことは、大切にしたい三つのことです。くどいようですが、「いのち・こころ・みらい」です。
一つ目「いのち」 命は、一人に一つだけしかありません。なくしてしまえば代わりはありません。自分の命も人の命も、どちらも大切にできる人になってください。特に、卒業、新たなる進路を目指す三年生のみなさんは、自己の体調管理をしっかりして、生活のリズムを整えましょう。
二つ目「こころ」 は、よく考えて行動し、心の力をつけようということです。二学期の終業式に話しましたが、難しいことではありません。例えば、進んであいさつをするとか、友だちに親切にするとか、「ありがとう」、「ごめんなさい」を素直に言えるようにすること。ちょっとしたことで、私たちの心はさわやかになり強くなれるのです。人の嫌がることをしない、されたら嫌だときちんと言う、誰かがされているところをみたら助けてあげる。
三つ目「みらい」 は、自分のかがやく未来に向かって、命と心を大切にして、さらに、しっかり学習して力をつけようということです。
今日から三学期、それぞれの学年のしめくくりの大切な学期です。充実した時間を過ごしましょう。
-
2学期終業式 式辞
- 公開日
- 2008/12/22
- 更新日
- 2008/12/22
校長室より
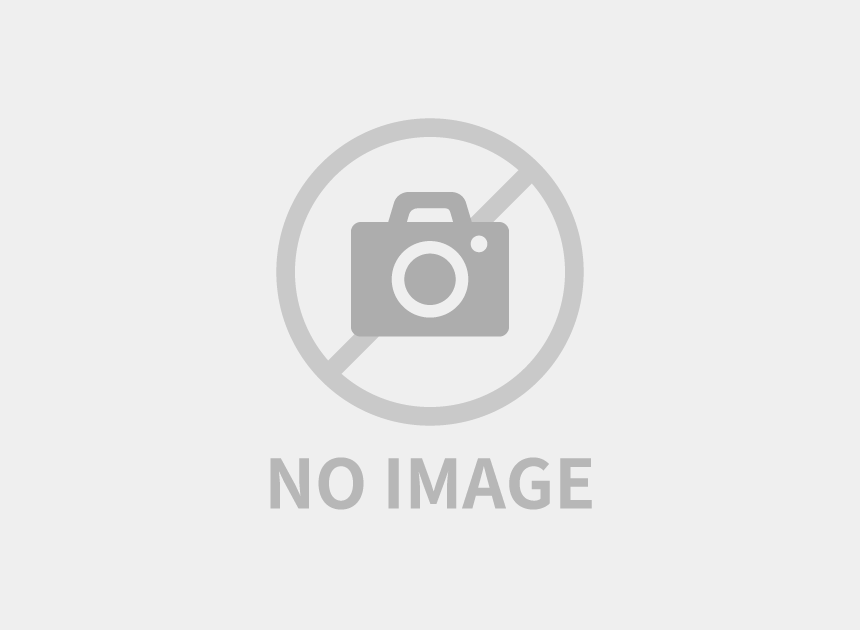
2学期終業式 式辞
2008年もあとわずか。二学期の終業式というよりも、みなさんにとっては冬休みの始まりというイメージでしょう。
さて、私は4月から折りあるごとに、みなさんに「命、心、未来 」の3つを大切にと言い続けてきました。今日は、その中の「心」の話をします。
今、心配していることがあります。それはみなさんの間で、やや攻撃的な言葉が日常的に飛び交っていることです。「言葉の暴力」と言っても過言ではなく、「言葉によるいじめ」だと言われても仕方ない。ちょっと考えれば、こんな言葉を使うと相手は傷つくだろうとすぐわかるはずです。言われた方も嫌ですが、言ってしまった人も何かストレスをためているのだと思います。ストレスはどんなときに感じるかと言えば、自分の意思と反することが起きたとき。例えば、突然勉強しなさいと言われたとき、身に覚えのないことで叱られたとき、悪口を言われているとき、親や先生に自分の言い分を聞いてもらえないとき。色々な場面で日常的に感じます。でも、そこでうまくかわす方法をもっていれば楽です。うまくストレスを発散し、ストレスに打ち勝つ方法を自分でつかんで欲しいと思います。例えば、一呼吸置くとか、気分を切り替えるとか、運動して発散するとか、音楽を聴いたり、話しをしたり、気持ちを紙に書いたり、好きなことをしたり、自分にあった方法を見つけましょう。すぐキレる人はいませんか?これも困ります。張りつめてばかりいるとキレやすくなるので、時には気を緩めて、ぼーっとする息抜きの時間も必要です。緊張ばかり続くとストレスが貯まります。緊張と緩和、このバランスをうまくコントロールすること。特に進路選択を迫られている3年生の皆さんは、うまくストレスと付き合う方法を獲得してください。
たった一言でうれしくなることがある、逆に何もかもイヤになることもある。何気ない、たった一言で、人を救うことも、傷つけることもある。だったら、1日1回でいいから、できる限り有効な一言を言ってみよう。思いつかなければ、「ありがとう」という言葉をたくさん使いなさい。
最後に、もう一つ確認しておきたいことがあります。「いじめ」と「暴力」は絶対にいけない。やっている本人がわからないときは、周りの人間が気づいて、とめてあげてください。
まもなくやってくる未来、2009年が、みなさんにとって、よりよい成長をもたらす年になることを祈っています。
-
吹奏楽部演奏会
- 公開日
- 2008/11/17
- 更新日
- 2008/11/17
校長室より
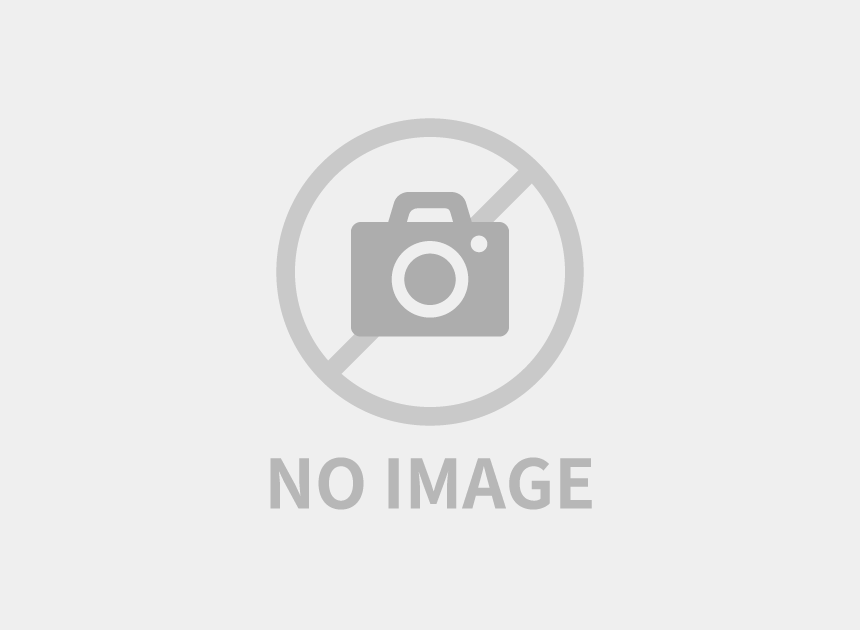
来場いただきありがとうございました
改めて、この鷹来中校区はすばらしい地域だと強く感じました。それは、地域に根ざした手作りの演奏会が開催でき、しかも、足元の悪い中、会場に入りきらないほどたくさんの方が来場してくださったからです。
日ごろお世話になっている地域の皆さんに、自分たちの演奏を聴いてもらいたいという、吹奏楽部員の熱い思い、そして、顧問の長谷川先生の吹奏楽部にかける熱い情熱からスタートしたこの演奏会は、もう7回目となりました。小さなお子さんから、お年寄りの方まで幅広い方々を対象に、吹奏楽の演奏を通して、音楽のすばらしさや楽しさを伝えるという、まさに芸術の秋に相応しいイベントです。部員の日々の努力に加え、保護者の皆さんのご理解とご協力、そしてこの鷹来中校区の地域の皆さんのお支えがあってこそ、このように継続開催できるのだと思います。
演奏会終了後、80歳を超える方から「毎年楽しみにしています」、本校吹奏楽部のOBの方からは「部員のみんなが生き生きとしている」、小学生からは「中学校に入学したら吹奏楽部に入りたい」などという声をいただきました。
吹奏楽部保護者会の方々は早朝より夕刻まで、会場の準備、機材の搬入、駐車場や会場の整理、受付、後片付けにいたるまでほとんどお手伝いいただき本当にありがとうございました。また、OBの方々をはじめ本演奏会の開催にあたり、種々のお世話をいただいた皆様にも心からお礼申し上げます。
鷹来中学校は、地域の方々に協力いただきながら、地域の子どもたちを健全に育成していく地域の中学校 です。オープンスクールなどで、地域の方に中学校に来校いただいたり、このように中学生が地域に出ていくという、相互交流をさらに活発に進めていきたいと思います。
-
春日井まつり
- 公開日
- 2008/10/20
- 更新日
- 2008/10/20
校長室より
18・19日に春日井まつりが開催されました。両日とも天候に恵まれ、会場の市役所周辺はものすごい人出でした。私も両日、イベント(野外造形展)の担当として会場にいました。
そんな中、まつりの運営に ボランティア として、本校の生徒が、たくさん参加・協力してくれたようです。ゴミの分別監視、イベントの補助など内容はさまざまでしたが、まつりの実行委員の方からは、どの中学生ボランティアもしっかりと仕事をしてくれたと評価いただきました。
また、郷土芸能の発表の舞台では、無形文化財 伊多波刀神社の流鏑馬が披露され、保存会の活動に参加している本校の生徒も出演しました。
地域のイベントに積極的に参加するだけでなく、裏方のボランティアとして働いたり、出演する側に回ったりして、まつりを盛り上げる経験をすることはとても意味のあることだと思います。これからも、生徒の皆さんには、積極的にボランティア活動等に参加してほしいと思います。 -
部活合同練習会
- 公開日
- 2008/10/14
- 更新日
- 2008/10/14
校長室より
三連休中に、市内の部活合同練習会(新人戦)が行われました。私もできる範囲でさまざまな部の生徒の活躍を見て回りました。
各部とも3年生引退後、2年生が中心となってチームを牽引してきました。夏の大会の時点でのチームと比べると、完成度も迫力も違いますが、初々しさや、ひたむきさなどが感じられ、応援にも熱が入りました。持てる力を十分に発揮して栄光をつかんだチームや、残念ながら実力を出し切れないまま敗退したチームがありました。しかし、どのチームもこの大会がゴールではなく、スタートのようなものです。これからさらに心身を鍛えて、来年の夏の大会では 全力を尽くせ るように、各自が目標を設定し、練習を続けてください。
三連休にもかかわらず、応援にきていただいた保護者の皆さん、また、引率、指導、大会運営などに協力いただいた先生方、ありがとうございました。
-
吹奏楽部の活動
- 公開日
- 2008/09/25
- 更新日
- 2008/09/25
校長室より
9月23日、角膜や腎臓を提供した春日井市の故人を顕彰する式典が総合福祉センターで行われました(春日井中央ライオンズクラブ主催)。鷹来中校区のライオンズクラブ会員の方の依頼により、本校の吹奏楽部がボランティアとして、この式典で演奏を行いました。吹奏楽部は学校と地域の交流の一環として、この他にも、11月に鷹来公民館でのコンサート(生指連主催)も予定しています。
今後も地域の中学生 として、ボランティア活動を含め、地域のいろいろな活動に積極的に参加してください。 -
始業式 式辞
- 公開日
- 2008/09/01
- 更新日
- 2008/09/01
校長室より
それぞれの充実した夏休みが終わり、今日から二学期が始まります。夏休み中には、各種大会や発表会などに学校代表として多くの皆さんが参加し、それぞれ成果をあげてくれました。また、それが終わって次の目標に向けて一・二年生を中心として、暑い中、一生懸命部活動の練習に参加した人も多かったと思います。そのほかにも、三年生の人たちは、自分の進路を考え、学習面でも多くの人が努力したことだと思います。常に目標を持って努力することはとても大切なことです。こういう経験はこれから先の皆さんの人生にとってとても意味のあることです。
さて二学期は落ち着いて学習に専念する時期であると同時に、体育大会、部活合同練習会、文化祭などの行事もあります。これらの行事は、クラスや部活の仲間、学年を超えた全校の仲間で協力しないとできないことばかりです。一学期よりもさらに充実した学校生活が送れるように全力を尽くしましょう 。学校には、信頼できる仲間や、あなたたちを大切に見守る先生方がいます。二学期もさまざまなことで悩んだり迷ったりする機会も多くなると思いますが、自分ひとりで悩まずに、友人や担任の先生、学年の先生、部活顧問の先生、スクールカウンセラーの先生、そのほかに自分が相談したいと思う先生、もちろん校長でも教頭でもかまいません、一人で悩まないで、ぜひ話しかけてください。
さて、もうひとつ、重要な話をします。本年度四月から、学校と地域との連携 についていろいろ地域の方々と話し合ってきました。地域の方は生活の基盤である自分たちの地域をよりよくしていきたい、という共通の思いをもっています。そのためには現状をよくすると共に、未来の地域社会を支える子どもたちを健全に育てることが大切だと考えています。そこで、まず、子どもたちとの交流の機会をつくろうと、オープンスクールなどで、学校にきていただき、皆さんの様子を見ていただくなど、少しずつさまざまな試みを始めています。同時に、皆さんが地域に出て行く機会 も必要だと思います。
天候不順で、延期になりましたが、先週の土曜日、大手地区のおやじコムネットのボランティア活動、地域安全パトロールと清掃活動に、本校の生徒が何人か参加する予定であったいう連絡も受けています。参加予定だった人、ぜひ次の機会には仲間も誘ってその輪を広げてください。
ボランティア以外にも、地域の活動に参加し、地域の方と交流する機会はあります。たとえば、今から紹介する伊多波刀神社の奉納流鏑馬(やぶさめ) です。流鏑馬は、馬の上から的を狙って弓を射るものです。鷹来地区では、戦国時代から昭和初期まで続いていた行事で、一旦は途絶えていましたが、平成になり地域の人たちの尽力で、また復興されました。春日井市の無形文化財にも指定されています。しかし、自分たちの地域にこのような歴史を持つ行事が継承されていることを知らない人も多いでしょう。保存会では、こういう地域の伝統文化を広く地域の方に知ってもらうためにも、中学生に参加を呼びかけています。興味のある生徒はぜひ見学に行ってください。案内は教室に掲示してもらう予定です。よくわからない人は、直接私に聞きに来てください。
この外にも、中学生が参加・協力できるさまざまな地域の活動 はありますので、これからもときどき紹介していきます。家庭と学校以外にも自分の活躍する場を積極的に見つけていきましょう。 以上で話を終わります。
-
地域の夏祭り
- 公開日
- 2008/08/06
- 更新日
- 2008/08/06
校長室より
酷暑 と呼ぶのが相応しいような厳しい暑さが続く毎日です。
夏季休業も半ばにさしかかり、部活動や学習相談なども一区切り、生徒たちにとって本格的な「休み」を迎えます。地域や家庭での生活が中心となりますが、基本的な生活習慣を崩さないようにしてください。特に体調管理にはご注意をお願いします。
さて、先日校区のある地区の納涼祭りを見学させていただく機会を得ました。準備、運営、後片付けと、すべて地域の方々の協力により、行われていました。子どもたちをはじめ、たくさんの住民の方が参加された盛大な催しでした。
会場では、地域のいろいろな方とお話ができました。30年近くにわたって、ラジオ体操の指導や子ども会の運営にあたってくださっている方、子どもたちの登下校の安全確保のため、毎朝、交差点で立哨指導をされている方、以前PTAの役員を務められ、現在も地域と子どもたちのためにボランティア活動を続けてくださっている方など・・・地域の方々がいかに地域や子どもたちを大切にしているのかがよくわかりました。
自分の親以外にも、多くの大人の目に見守られて健全に育っているこの地域の子どもたちは恵まれていると思います。そう考えると、その子どもたちが通う中学校としては、もっと魅力のある、地域からも信頼される学校にしていく責任があると改めて感じました。今後も地域の方にご支援、ご協力をいただきながら、よりよい学校作りを目指して努力していきたいと思います。
祭の会場から少し離れた駐車場では、数名の方が誘導や整理をされていました。快く迎えていただき、快く送り出していただきました。華やかな祭りの表舞台だけではなく、こうした見えないところにまで配慮をしてくださっていることに対し、感動を覚えました。自分にとっては本当に有意義な時間でした。 -
部活動、夏の大会・発表会
- 公開日
- 2008/07/29
- 更新日
- 2008/07/29
校長室より
出校日の全校集会で、部活動の市大会・発表会についての伝達表彰をし、私が見て回った感想を話しましたので、ここに紹介します。
部活動、夏の大会・発表会の感想
たいへん暑い中、春日井市の大会・発表会が終わりました。教頭先生と手分けをして、学校代表の皆さんの応援に回りました。そんな中、印象に残った場面をいくつか紹介します。
野球部、1回戦の追加点がほしいという場面で鮮やかに決めたスクイズ。野球は打つ、投げる、走る、守るなど個人の技もすばらしいのですが、サインひとつにみんなが集中する場面が最高です。決まったときは思わず「よし!」と声を出してしまいました。
サッカー部、1回戦、サイド攻撃から切り込んで、角度のない位置からのシュートがキーパーをすり抜けてゴールが決まったシーンが印象に残りました。
男子バスケットボール部、2回戦、追いつかれるとすぐに決めた鮮やかな3ポイントシュート。きれいなフォームから放たれたボールが、スポッとゴールに吸い込まれるところが印象的でした。毎日こつこつと何本も練習した成果が試合で発揮されたのだと思います。
ハンドボール部、相手の固いディフェンスに苦戦しながら、一瞬の隙を突いて打ったミドルシュートがゴールに突き刺さった場面にはしびれました。
ソフトテニス部は個人戦を見ました。ゲームを先攻され、追い込まれてからの土壇場での粘りの逆転勝利、ボールがネットにかかりながらも相手のコートに落ちた場面が印象的でした。
卓球部も個人戦でした。2回戦の強い相手に対しても、ラリーで一歩も引かず、逆に相手を追い込んでいく場面が印象に残っています。
バドミントン部も個人戦でしたが、自信を持って相手を圧倒した女子ダブルスの試合、強い相手に一歩も引かず善戦し、ゲーム終了後に倒れそうになるまで動いた男子シングルスの試合に感動しました。
剣道部、応援に行きましたが、試合時間が合わずに残念でした。女子バレー部、女子バスケ部の試合はどうしても調整できず、見にいけませんでした。ごめんなさい。
吹奏楽部の発表会、本校は堅苦しい演奏ではなく、演奏者も観客もともに楽しめる感じの内容でした。私の周囲にいた観客の評判もとてもよかったです。
英語のスピーチコンテストも、出だしはちょっぴり緊張気味でしたが、堂々と最後までスピーチできたと思います。
演劇部、顧問の先生方の協力を得ながら、少ない人数でもよく努力を重ねたりっぱな舞台でした。
どの選手も今もてる力を十分に出し、全力を尽くせ たと思います。また、次の新しい目標を設定し、それに向かって、全力を尽くしてください。感動は言葉では伝えにくいものですが、私の感動を少しでも皆さんに伝えたいと思い、今日はこんな話をしました。
県大会に出場する選手の人は、鷹来中の他の部活の分まで、十分にその力を発揮するとともに、県大会という舞台を楽しんできてください。
-
1学期を終えて
- 公開日
- 2008/07/29
- 更新日
- 2008/07/29
校長室より
遅くなりましたが、一学期の終業式で生徒に話したことを紹介します。
終業式 式辞
今日は担任の先生から、通知票を渡される日です。一学期のみなさんの学校生活の様子をお知らせする大事なものです。出席の様子、係や委員会や部活など、そして教科の学習の様子が書いてあります。そして、教科の学習では、どの教科も真っ先に「関心・態度」という項目があります。その教科にどれだけ前向きに取り組んだかという項目です。その後に、それぞれの教科ごとの項目があって、最後にそれらをまとめて5とか1とかの数字があります。ただ、通知表で示される評価は、あなたがた一人一人の人間としての評価を決め付けるものではありません。一学期という時期に、教科の観点からみるとこうなりますよというお知らせですから、他の生徒と比べて、どちらが優れているかという比較に使うものではありません。現時点が人間としてのゴールではありません。まだまだ、これから先は長いです。だから、今の時点での自分に不足している点や必要な点、反対に十分できている点などを確認し、次のステップに利用するためのものが通知表です。それぞれ、一学期の取り組みを振り返って、明日からの取り組みの参考にしてください。
さて、始業式に皆さんに、大切にしてほしい3つのこと「命、心、未来」について話をしました。覚えていますか。
一つ目、命を大切にしよう。自分の命も他人の命も、どちらも大切に。
二つ目、心を鍛えよう。難しいことではなく、仲間や弱い立場の人、困っている人に優しくしよう。
三つ目、自分の未来に向かって、命と心を大切にしながら、しっかり学び、生きる力をつけよう。
通知表と同じく、現時点で完成というものではありません。現在どの程度意識して、生活しているかが重要なのです。忘れていた人は思い出してください。そして、夏休み中もこの3つを意識して生活をしてください。
明日から夏休み。家庭や地域で過ごす時間が多くなります。自分を大切に、友だちを大切に、かけがえのない命に磨きをかけて、二学期にはいっそう成長した姿を見せてください。これで、お話を終わります
-
待つ、我慢する
- 公開日
- 2008/07/07
- 更新日
- 2008/07/07
校長室より
最近の子どもたちを見ていて、対人関係を構築する能力や我慢強さ(耐性)が弱くなってきたのではないかと感じます。先日参加した「東海北陸中学校長研究協議会」の進路指導に関わる研究部会で、興味深い調査結果の報告がありましたので紹介します。
高校における退学者の傾向
①生徒指導面の問題(校則等遵守できない)
②学力面の問題(授業が面白くない、内容がわからない)
③対人関係の問題(友人が作れない、仲間関係のもつれ)
④家庭の問題(経済的理由)
⑤進路指導の問題(中学校側の指導のミスマッチ)
高卒後の早期離職者の能力的要因
①コミュニケーション能力の不足
②計算力・知識・学習能力の不足
③対人関係不安
④身体的能力不足
⑤職業観の軽薄さ(アルバイト感覚)
⑥自己肯定感の未熟さ
まさに私の危惧する「対人関係能力の低さ」や「我慢強さ(耐性)の欠如」を裏付けるような調査結果だと思います。
さて、現代社会は確かに便利な環境にあります。冷凍食品やインスタント食品、各種自動販売機、24時間営業のコンビニ、携帯電話、メール、インターネット、家庭用ゲーム機などが普及し、生活に入り込んでいます。いつでもどこでも自分の欲求を充たす活動ができます。空腹になればすぐ何かを食べられる、誰とでもすぐ連絡が取れる、家にいても買い物ができる、夜中でも店は開いている、好きなゲームはやり放題というような状況です。つまり、「待つ」必要がない社会となりつつあります。
だから、待てないそして我慢もできません。お腹が空いたら、公共の場でもどこでもかまわず何かを食べます。家まで我慢できないと学校帰りでも買い食いをします。夕飯の準備が遅れれば、自分だけ勝手にお菓子を食べます。すべて自分の欲するままに行動し、思い通りにならないと限界が浅いからすぐキレてしまいます。それを対人関係にまで持ち込むため、トラブルも多いです。集団遊びの経験が少ないので、仲間との折り合いのつけ方や調整の仕方も苦手なようです。それぞれが勝手な行動に終始し、相手を気遣うこともできず、気ままで希薄な人間関係となりがちです。嫌いな子は徹底して嫌い、好きな子は徹底して好き、感情優先で理性的な側面はあまり見られません。したがって、行動の判断基準は客観的な善悪ではなく、個人的な好き嫌いや快楽、友人との間に互いに切磋琢磨するなどという感覚はあまり見られません。
もちろん、すべての子どもがこのような状態にあるとは思いません。しかし、まだまだ未発達な子どもたちですから、どうしても安易で楽な方向には流されやすいと思います。一方で、その心は未成熟であり、自己肯定感は低く、常に不安を抱え、傷つきやすく、悩みやすく、落ち込みやすいようです。人間関係がめんどうになると自分の殻に閉じこもってしまう恐れもあります。
このままではいけないと思います。まず、私たち大人が、子どもたちにしてあげられることから実行しなければ・・・。家庭で、学校で、地域で、さまざまな機会に「待つこと」や「耐えること」を教え、具体的に体験させていくことが必要ではないでしょうか。
-
進路説明会
- 公開日
- 2008/06/20
- 更新日
- 2008/06/20
校長室より
進路説明会(6月20日)に多くの保護者の方に参加いただき、ありがとうございました。
会の冒頭の校長あいさつでお話した内容を以下に紹介します。
今日は、進路の自己責任ということに絞って、3つ話をします。
1つ目 心構え
今があって、未来がある。いきなり未来は始まらない。就職試験も入学試験も偶然に合格することはない。自分の日々の努力の結果という必然があって合格する。ただし、就職や入学試験という近い未来だけではなく、自分の長い人生の遠い未来まで見据えた選択をしてください。
2つ目 自己決定
進路は自分で決めるもの。ただし、決めるための情報提供やアドバイスは学校でも精一杯させてもらいます。しかし、決めるのは自分です。当然、結果についても自分で責任をとるのです。自分に必要な情報を集め、先生やお家の方のアドバイスを参考に、思い付きではなく、よく考えて、自分で責任を持って決めてください。
3つ目 推薦
進路先からよく「いい子がいたら推薦してください」と言われます。「いい子」というのは「進路先での約束事を守って前向きに努力する子」 という意味です。例えば本校では「若鷹」を使って生活についての決まりを示しています。違反していると先生方から指導は受けますが、大きな罰則はありません。しかし、『先生から注意されても大きな罰などないからいいんだ』と言って生活面が乱れている子は「約束事を守って前向きに努力する子」として推薦することはできない。それも自己責任です。
自己責任について3つ話をしました。学校は基本的にみんなを応援する姿勢です。しかし、決めるのは自分だし、自分で努力しない子は応援の仕様もないよ……そういうことが言いたかったのです。今からでも遅くはありません。未来に向かって努力 する気になってください。
-
地域交流活動 −オープンスクール−
- 公開日
- 2008/06/18
- 更新日
- 2008/06/18
校長室より
学校支援地域交流活動
近年、都市化、核家族化、個人主義の浸透、地域における地縁的なつながりの希薄化などに伴い、家族や地域の絆が弱くなってきたように感じます。また、子どもたちにとって、地域の大人とともに様々な経験をする機会は減少し、その経験から学んでいた「社会性」や「人との信頼関係」を作り上げていくことがやや困難となっています。
そこで、将来の社会を担う子どもたちの健全な育成を目指すためにも、地域の大人が積極的に学校に関わっていただくと同時に、子どもたちも地域の活動に関わっていくこと、いわゆる学校と地域との連携が重要だと思います。もちろん、一朝一夕にしてできることではありませんが、まず、できることから着手していきたいと思います。その第一歩として、地域の中であまり存在感のない「中学生」の姿を見てもらおうと、本年度から地域を対象としたオープンスクールの開催を計画しました。
オープンスクール
6月9日(月)から13日(金)までの5日間、150余名の方に来校いただきました。
お忙しい中、足をお運びいただき、ありがとうございました。
本年度は中学校の保護者の方だけではなく、鷹来小、西山小、大手小の協力を得て、小学校の教員や保護者の方にも多数来校いただきました。ふだんの中学校の様子を知っていただくよい機会になったのではないかと思います。
次回のオープンスクール開催は10月を予定しています。小中学校の保護者の方だけでなく、地域の皆様にも来校いただけるように自治会・町内会等の回覧板などを通して、ご案内できたらと考えております。
来校者の方から、一言感想を書いていただきましたので、その中から、共通する内容を一部紹介させていただきます。
・ 授業中は思ったよりも静かである 21
・ 自分の目で見て、安心した 18
・ 思ったより、落ち着いている 15
・ 机に伏せて(寝て)いる生徒がいる 12
・ 生徒のほうから、あいさつをしてくれた 10
・ 思ったより、校舎内がきれい 9
・ 教師は態度のよくない生徒にきちんと注意をすべき 7
・ 授業中の私語が多い 5
・ 一部の生徒に集中力・落ち着きがない 5
中学校に対する負の印象が、少し払拭できたと思いますが、学校側として反省すべき点も多数ご指摘いただきましたので、謙虚に受け止め、今後の学校運営の参考にさせていただきます。貴重なご意見をいただきありがとうございました。
今後も、地域の学校、開かれた学校を目指して、職員一同努力していきたいと思います。ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。
-
5月集会講話
- 公開日
- 2008/05/01
- 更新日
- 2008/05/01
校長室より
風薫るさわやかな季節となりました。もう5月です。
今朝の集会で生徒に話した校長講話の内容を紹介します。
一年生の皆さん、学校には慣れましたか。二年生、三年生の皆さん、順調にスタートできましたか。全校の皆さん、学校生活で困っていることはありませんか。
明治のはじめ、札幌農学校の責任者としてクラーク博士が日本にやってきました。彼は「ボーイズ・ビー・アンビシャス」(少年よ大志を抱け)ということばで有名ですが、その札幌農学校では「きまり」はたった一つだけだったそうです。それは「ビー・ジェントルマン 」(紳士であれ)という一言でした。生徒たちは、この行いが紳士的かどうかを自分で判断し、やっていいこといけないことを自分で決めたそうです。「紳士的」という言葉は、直訳です。女性の方には申し訳ないですが、他に表現する言葉が思いつかないので使いました。
ここまでやっても罰せられないからやってもいい。
これをやっても見つからなければ、わからなければかまわない。
誰かが困っているけれど自分のことじゃないから関わらないでおこう。
そういう考えは情けないですね。鷹来中学校の生徒は、規則でしばりつけ、規則を守っているかをいつも見張っていなければ学校生活ができないような人間ではない。また、困っている人がいても見て見ぬふりをしているような、そんな情けない人間ではない。私は信じていますし、強く期待しています。
新年度が始まって1ヶ月、今一度自分を振り返り、そして自分たちのクラスや学年集団を振り返ってみましょう。みんなの力で気持ちのよい、楽しい学校にしていきましょう。
ルールは大切ですが、マナー はもっと大切です。周りのこともよく考えた行動を!
-
ご挨拶
- 公開日
- 2008/04/16
- 更新日
- 2008/04/16
校長室より
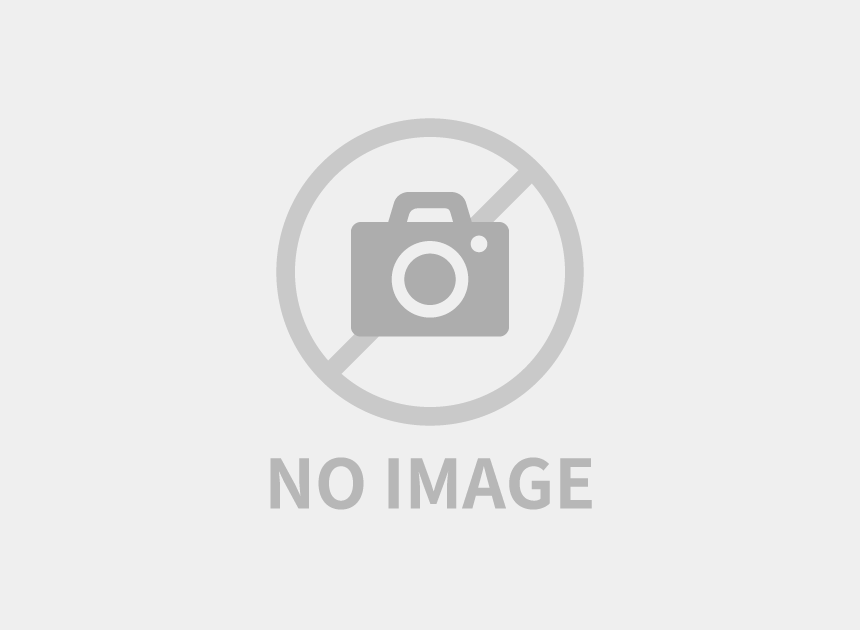
この4月から鷹来中学校に赴任した校長の伊藤孝之です。
私の学校経営の基本にある考えは「みんなの楽校(学校)」を作るということです。
「みんな」というのは主役の生徒だけではなく、保護者や地域の方、職員などこの学校にかかわるすべての人を意味します。生徒にとっては楽しく通える学校、保護者にとっては安心して通わせることができる学校、地域の方にとっては信頼できる学校、職員にとっては働き甲斐のある学校になるようにと考えています。みんなの手でこの鷹来中学校をすばらしい学校に作り上げていけたらと思っています。
保護者の皆さん、地域の皆さん、ご協力・ご支援をよろしくお願いします。
さて、「学校だより」でも紹介しましたが、始業式の式辞をここに紹介します。
かけがえのない自分の存在と「命」「心」「未来」を大切に!
二度とない今という時間を充実させ、かけがえのない自分という存在を大切にしよう。そのための3つのキーワードを示します。それは「命」「心」「未来」です。しっかりと覚えておいてください。
(命)自他の生命を大切にし、健康で生き生きと生活しよう。
(心)善悪についての判断力を養い、仲間や弱い立場の人に対して、優しさや思いやりの気持ちを持ち、互いに尊重し合って生活しよう。
(未来)なりたい自分になるために、夢とやる気を大切にしよう。そのためには、基礎的な学習内容を確実に習得するための努力を怠らないようにしよう。
さあ、自分たちの手で充実した楽しい中学校生活を目指そう。若鷹よ、輝く未来に向かって「全力を尽くせ!」