-
8月31日 6年生 市長を囲んでわくわくトーク(7/30)
- 公開日
- 2021/08/31
- 更新日
- 2021/08/31
6年生
7月30日に文化フォーラム春日井にて、春日井市内の各小学校6年生代表が市長と語り合いました。
牛山小学校の代表の子も、市長さんに伝えてきたことがあるようです。どんな内容だったかは、明日発表する予定です。 -
8月27日(金曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り 6
- 公開日
- 2021/08/27
- 更新日
- 2021/08/27
お知らせ
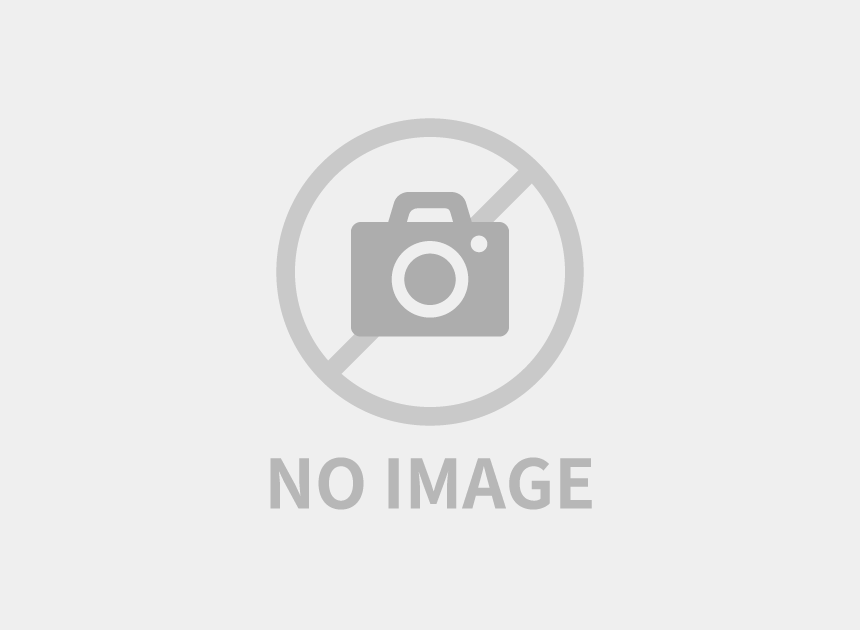
時間の位取りで10進法のものは、小学生でもなじみがあるものがあります。それは1秒よりも小さな時間のことで、体育の競技のタイムでよく目にします。たとえば50m走では8.9秒と表記しますし、陸上男子100mの世界記録はボルトの9.58秒と書きます。
10進法の基になっているメートル条約は1875年にパリで締結されました。これ以後、国際的にメートル法が使われるようになるのですが、なんと時間は決議されていません。実は10進法の時間を設定しようという議論もあったようなのですが、フランス革命の失敗を覚えていたのでしょう。そこで、それまでの12進法と60進法がそのまま使われることになり、
地球の自転を基に、1秒=1日の1/86400(24×60×60)としました
ただし、1秒以下については10進法が導入されたようです。実際に使用された記録については、近代オリンピックのものがあります。1886年の第1回アテネ大会の陸上競技の100mが12.0であり、世界公認記録としては第5回ストックホルム大会の10.6という記録が残っています。ただ、測定器はストップウオッチで、しかも手動でした。
ところが、この1秒が後に天文学的観測から一定でないことが判明します。
自然の現象ですから当然と言えば当然です。
1956年になると、国際度量衡委員会で、地球の公転を基とすることが決められました。地球の自転よりも変動が少ないというのが理由でした。しかし、定義を見ればわかるように、これも一定ではないことが明らかですね。
そんななか、イギリスでセシウム133原子時計が開発されました。これが時間の定義の大きな転機となりました。1967年〜セシウム原子の出す電磁波の周波数による定義に変更されることとなったのです。原子時計の誕生で、固定した時間が測定可能となったためです。そこで、
1秒=「セシウム133原子が91億9263万1770回振動する時間」と再定義しました。
そして、現在の時間はこの1秒を基準に再構築されることとなりました。さらに、原子時計がこれだけの精度であることから、1秒以下の時間も正確に測定、規定できるようになったのです。
その1秒以下の時間として、
ミリ秒 (1/1000秒)
マイクロ秒(1/1000000秒)
ナノ秒 (1/1000000000秒)
ピコ秒 (1/000000000000秒)
が設定され、ご覧のとおりすべて10進法で構成されることになったのです。ちなみに、現在のコンピュータで扱う時間は、ミリ秒を最小単位としています。
つまり、現代の時間は、古代からの取り決めを基にしてはいるものの、現代科学の粋を集めて定義し直したものを使用しているということになるわけです。 -
8月25日(水曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り5
- 公開日
- 2021/08/27
- 更新日
- 2021/08/27
お知らせ
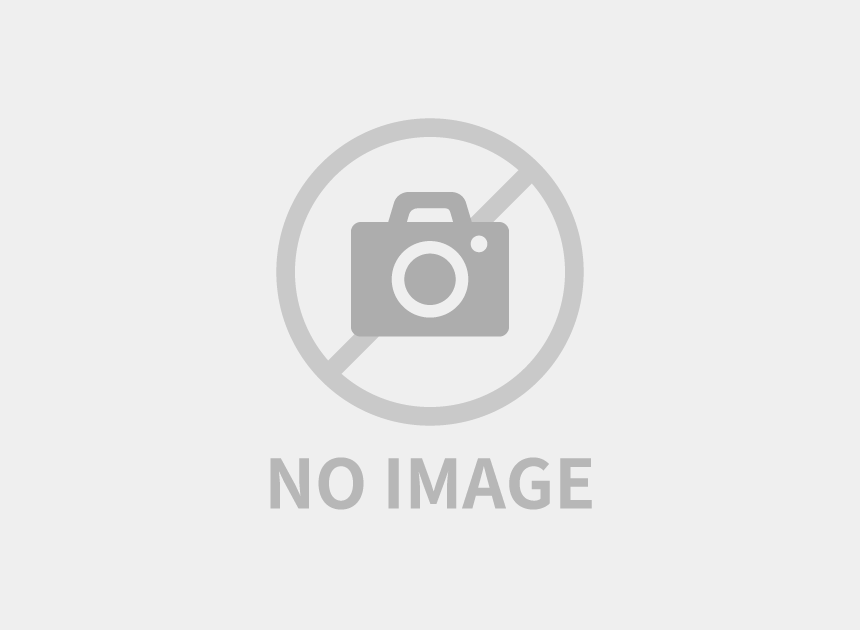
12進法と30進法についてはもう少し触れておきます。
そもそも12進法は、月の満ち欠けが元になっています。つまり、1月〜12月が12進法の元です。これはダースの元になったとも考えられ、ヨーロッパではメジャーな位取りであるとわかると思います。
そして、これは30進法とも関連があります。ただ、30進法については微妙な歴史があります。
月の満ち欠けは29.5日です。そこで、古代の人は太陰暦(正確には太陽太陰暦)として、1月から30日と29日を交互に置きました。すると、354日(30日×6+29日×6)となるので、365-354=11日を2〜3年で1か月としてまとめ、閏月を置いたのです。つまり、13か月の年があったのです。
それを太陽暦(現代のカレンダー)として、1月3月5月7月8月10月12月は31日、4月6月9月11月は30日、2月は28日として365日とし、余った約6時間を4年に一日としてまとめ、閏日を置いたのです。つまり、それが2月29日です。
フランス革命では、それをすべて30日にして360(30×12)日とし、残った5日を年末に置いて休日にしました。つまり、30進法に統一したという画期的なカレンダーになったわけです。しかし、それまでの伝統や他国との兼ね合いなどから、やはり使いにくいということになって廃止されたのです。
これで、10進法、12進法、30進法、60進法を解説してきました。しかし、時計には、ここまでに触れていない、明らかな10進法の仕組みの部分があるのです。次回はそこを取り上げます。
-
8月23日(月曜)5組 水遊びをしました
- 公開日
- 2021/08/23
- 更新日
- 2021/08/23
5組
野菜の収穫後に、みんなで水遊びをしました。段ボールに的の絵をかいて、水風船を投げて遊びました。水風船を作るのに苦戦している子も多かったですが、とても楽しんでいました。
-
8月23日(月曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り4
- 公開日
- 2021/08/23
- 更新日
- 2021/08/23
お知らせ
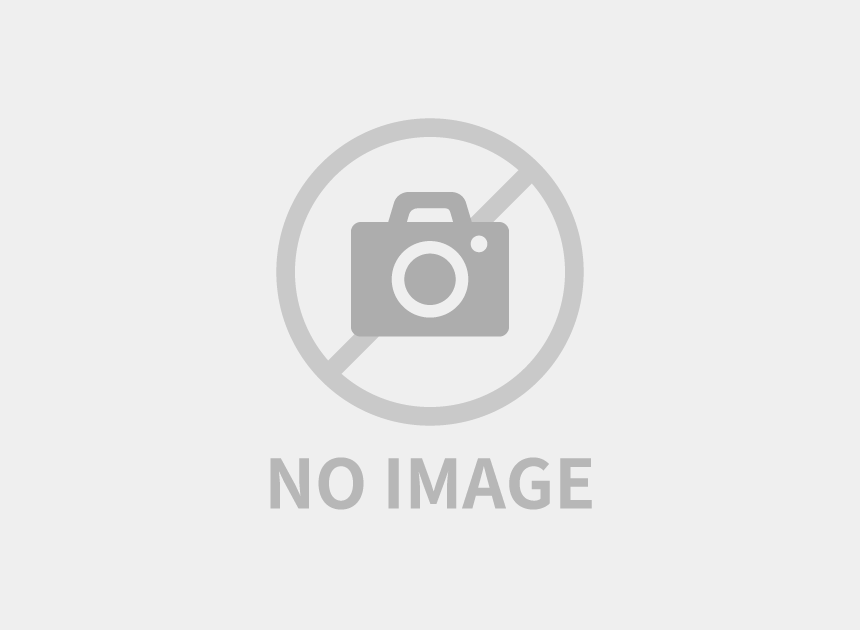
もう1つのメジャーな位取りが10進法です。これは人の指の数というのが有力です。今では位取りの基本中の基本であり、数字と言えば、特に断らなければこの10進法であることは周知の事実です。きっと、昔の人は指を折って数を数えたのでしょう。
手の指の数=10本
そして、この10と、前回に取り上げた12の最小公倍数が60となります。60進法は身近なものとは言いがたいのですが、実は、角度と密接な関係があるのです。
1周=60分 1周=360度
と、一見、関係ないように見えます。しかし、小学校ではなかなか教えないのですが、1度以下の角度は、次のようになっているのです。
1度 =60分=3600秒 (1分=60秒)
どこかで見た関係ですよね。そうなんです。実は、
1時間=60分=3600秒 (1分=60秒)
と、「分」「秒」の単位が角度と時間で共通しているのです。
60進法は、紀元前2000年頃にバビロニアの人々がさまざまな計算に用いていたことがわかっています。それを、紀元前2世紀の古代ギリシアの人々が受け継ぎました。
1日を等しく24時間に分けることを提案したのは、古代ギリシアの天文学者ヒッパルコスであり、彼を含めて古代ギリシアの天文学者たちは、天文学の計算に60進法を用いていたのです。それが時計に使われたということになるわけです。
-
8月23日(月曜)5組 野菜の収穫をしました
- 公開日
- 2021/08/23
- 更新日
- 2021/08/23
5組
1か月ぶりに5組の畑へ行き、野菜を収穫しました。夏休み前に比べて、オクラやピーマンが大きく育っているのを見て、とても驚いていました。
-
8月23日(月曜)出校日のようす
- 公開日
- 2021/08/23
- 更新日
- 2021/08/23
行事・生活
今日は夏休みの出校日でした。
朝の登校時は大変な雨と雷でしたが、
すぐに過ぎ去りました。
どの子も久しぶりに顔を合わせたのですが、
しっかりした表情と声であいさつしてくれました。
朝、教室をのぞくと、みんなで掃除をしていました。
降りこんだ雨や工事の塵などをよく拭いてから
1時間目と2時間目に臨んでいました。
コロナ感染症でまだまだ心配ですが、
感染対策をしっかりしていきたいと思います。 -
8月17日(火曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り3
- 公開日
- 2021/08/23
- 更新日
- 2021/08/23
お知らせ
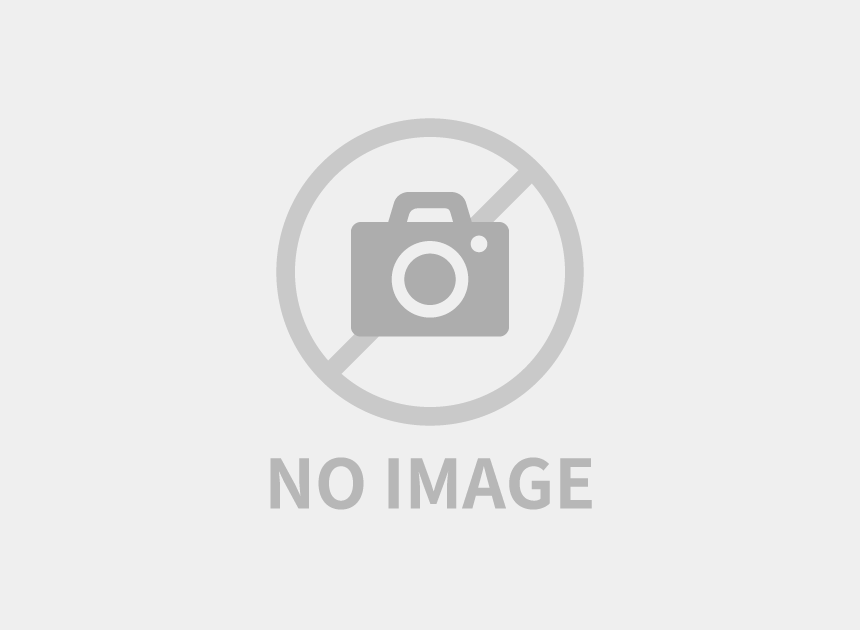
12進法と60進法に落ち着いたのは、時計の歴史から見るとこうなります。
機械時計の針で最初に登場したのは、「時針」、つまり、時間を指す針1本だけでした。つまり、時計はまずは時間だけを指し示す機械だったのです。そして、これが右回り、いわゆる時計回りでした。それは、南に向けた日時計の影の動きが元になっていると言われています。
そこに、技術が発達して、「分針」、分を指す針が加わります。つまり、よく見る短針(時針)と長針(分針)の時計になります。時計の技術史では、この分単位で正確に時間を刻めるようになるのにかなりの年月がかかっています。これはガリレオとホイヘンスが振り子を元に確立し、その後、この振り子を小さくして懐中時計に収めるために脱進機を発明、改良していったのです。
さらに技術が発達して、「秒針」、秒を指す針が加わります。まずは文字盤の6の上に小さなダイヤルをつけて、そこに小さな秒針をつけたのです。これをスモールセコンドと言います。そして、軍用に腕時計が登場すると、見やすさを追求した結果、時針・分針と同じところに長い秒針をつけたのです。これをセンターセコンドと言います。
これらの間に、フランス革命があって、ほんの一時(いっとき)、時計にメートル法(10進法)を採用し、
1日 =10時間
1時間=100分
1分 =100秒
を適用しようとしました。しかし、実際に使ってみると、使いにくいということで結局は定着せず、12進法と60進法が定着していった、という歴史だったのです。
つまり、時針、分針、秒針、と、それぞれ数百年もかけて、人が使いやすいものに改良していくなかで固定していったのが、12進法であり、60進法だったわけです。
-
8月6日(金曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り2
- 公開日
- 2021/08/14
- 更新日
- 2021/08/14
お知らせ
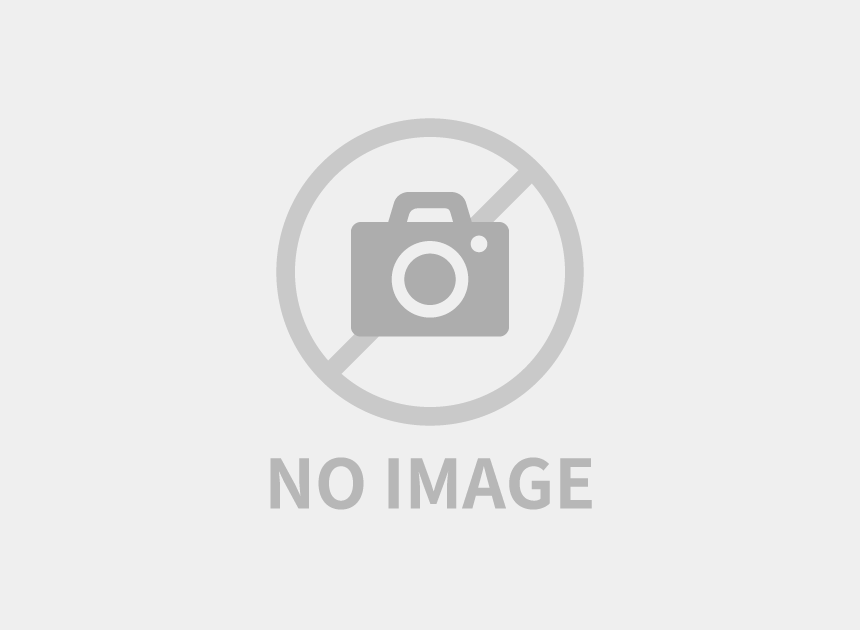
まずは、イ・ウから整理してみます。
これは要するに、時間を10進法で表すもので、メートル法ならこうなります。
実際、
1日 =10時間
1時間=100分
1分 =100秒
となります。私の知っている限りでは、この表示は、実際の世界ではフランス革命のときに定められた歴史があります。架空の世界ではアメリカのSFドラマ『スタートレック』に出てきます。
一見、合理的で使いやすそう、ですが、実際にはそうでもないことに気づきます。
例えば、1/3日 =3.33…時間
1/6日 =1.66…時間
1/3時間=0.3333…時間=33.33…分
1/6時間= =16.66…分
つまり、小数が出てきてしまって扱いにくいわけです。一見、万能に見える10や100という数字は、自然数の世界なら問題はないのですが、1以下の世界になると不便極まりないということになります。
その点、12(24)と60は実に便利です。
1/2日=12時間 1/2時間=30分
1/3日=8時間 1/3時間=20分
1/4日=6時間 1/4時間=15分
1/5日=4.8時間 1/5時間=12分
1/6日=4時間 1/6時間=10分
ということは、実生活では直観的に量で把握することができるということです。これは考えてみれば実によくできていると言えざるを得ない。
ということで、10時間や100分では、時計を読んだり、伝えたりするのは、不便なのです。それは、子どもが学習する際にも共通しています。しかも、12と60を使った時計の表示は、分数の学習の下地にもなっているのです。 -
8月5日(木曜)教頭と確認する学習内容 時計とカレンダーの位取り
- 公開日
- 2021/08/14
- 更新日
- 2021/08/14
行事・生活
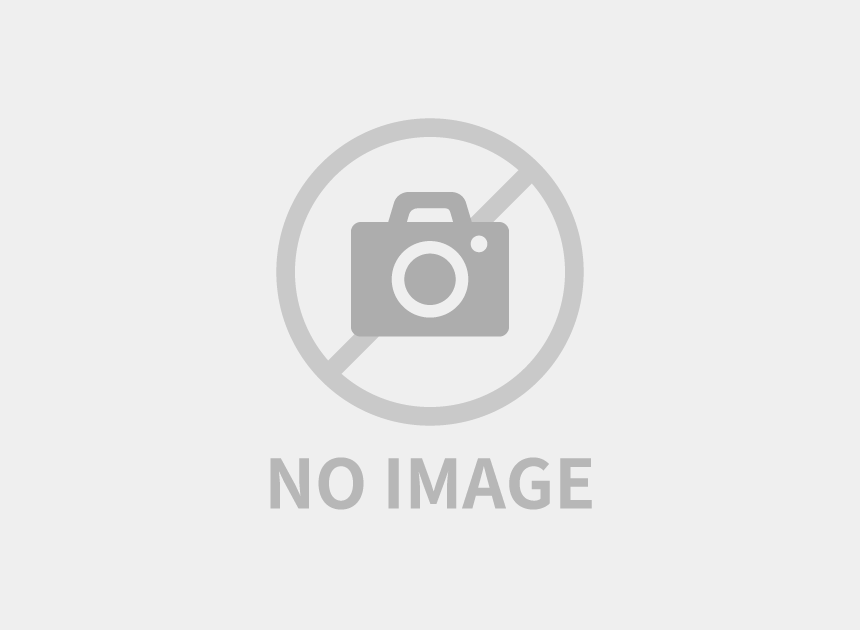
時計とカレンダーの内容は教え込みになりがちです。なぜなら、すでに存在する時計とカレンダーを、生活のなかでまずは読めるようにすることが最優先となるからです。
時計は2年生の学習内容のため、めざす技能は時や分を読むことのみが求められるからなおさらです。2年生以後はほとんど学習する機会はありません。カレンダーにいたっては低学年にはしっかりと教える機会はなく、高学年になってからの理科の月の運行のところで触れる程度と思います。
しかし、時計やカレンダーを構成している決め事は、実は意外と奥深いことに驚きます。
ア 時計の針は、なぜ右回りであり、左回りではないのか?
イ 1日は、なぜ10時間ではないのか?
ウ 1時間や1分は、なぜ100分・100秒ではないのか?
エ それなのに、1秒以下は、なぜ100ミリ秒や10ミリ秒で表すのか?
オ 1年は、なぜ10か月ではないのか?
カ 1か月の満ち欠けは29.5日なのに、なぜ実際は28〜31日なのか?
メートル法が基本であるなら、時計も10進法にしておけば学習する子どもたちも楽なように思うのですが、実際は、10進法あり、12進法あり、30進法あり、60進法あり、となっていて、その組み合わせになっているのです。考えて見れば、摩訶不思議な存在なのが時計やカレンダーなのです。
そのため、ほとんどの子どもは、意味など問わずにこういうもんだというレベルで済ませているはずです。しかし、一旦足を止めて、実際はどうなのかと問われると、大人でもすぐには答えられないことばかりです。
これから、時間ができたときに1つずつ取り上げてみたいと思います。


