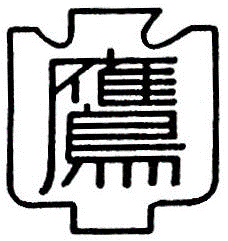生徒指導上の諸問題に関する調査結果から
- 公開日
- 2009/12/01
- 更新日
- 2009/12/01
校長室から
11月30日、文部科学省から平成20年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(暴力行為、いじめ等)が公表されました。新聞等でも報道されたので、ご存知の方も多いと思います。中でも、中学生の暴力行為は過去最高の4万件を超えた そうです。先月、沖縄県うるま市で中学校の同級生らによる暴行事件が相次ぎ、14歳の男子生徒が死亡、女子生徒が重傷を負った事件もありました。
文部科学省は、都道府県教委の分析として「自己の感情抑制ができない」「規範意識の低下」「家庭の教育力の低下」 などを増加理由に挙げています。また、暴力の背景には、日常的に子どもたちが親しんでいるメディア(インターネットやマンガ、テレビのバラエティ番組など)の言語表現が荒れ、感情や感覚の直接的な表現が主流 になっていることもあげられると思います。その影響を受けた子どもたちは深い思考や、自分の感情をいったん受け止めてから表現するということが苦手になります。したがって、自分の感情を抑えられないまま、教師や仲間と対立したときに、自分を抑えて引くという行為ができず、つい手を出すという状況となります。
善悪の判断を体得すべき時期である小学校低学年のころまでに、大人に厳しく叱られるという経験が少ないままで、中学生になった子どももいるのかもしれません。やはり、小さいうちに家庭で「あいさつ」「場に応じた正しい言葉遣い」「他人に迷惑をかけない」などのごく基本的な生活習慣を体得させ、地域や学校という社会で、他者と関わり合いを通して、それを確認しながら、身につけていくということが大切だと思います。
暴力行為だけではなく、問題行動を起こす子どもたちの背景は複雑です。家庭と地域と学校が連携 して教育に当たることが必要だと、改めて強く感じました。