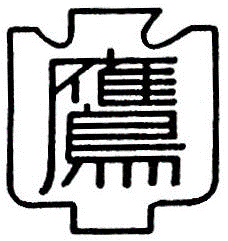待つ、我慢する
- 公開日
- 2008/07/07
- 更新日
- 2008/07/07
校長室より
最近の子どもたちを見ていて、対人関係を構築する能力や我慢強さ(耐性)が弱くなってきたのではないかと感じます。先日参加した「東海北陸中学校長研究協議会」の進路指導に関わる研究部会で、興味深い調査結果の報告がありましたので紹介します。
高校における退学者の傾向
①生徒指導面の問題(校則等遵守できない)
②学力面の問題(授業が面白くない、内容がわからない)
③対人関係の問題(友人が作れない、仲間関係のもつれ)
④家庭の問題(経済的理由)
⑤進路指導の問題(中学校側の指導のミスマッチ)
高卒後の早期離職者の能力的要因
①コミュニケーション能力の不足
②計算力・知識・学習能力の不足
③対人関係不安
④身体的能力不足
⑤職業観の軽薄さ(アルバイト感覚)
⑥自己肯定感の未熟さ
まさに私の危惧する「対人関係能力の低さ」や「我慢強さ(耐性)の欠如」を裏付けるような調査結果だと思います。
さて、現代社会は確かに便利な環境にあります。冷凍食品やインスタント食品、各種自動販売機、24時間営業のコンビニ、携帯電話、メール、インターネット、家庭用ゲーム機などが普及し、生活に入り込んでいます。いつでもどこでも自分の欲求を充たす活動ができます。空腹になればすぐ何かを食べられる、誰とでもすぐ連絡が取れる、家にいても買い物ができる、夜中でも店は開いている、好きなゲームはやり放題というような状況です。つまり、「待つ」必要がない社会となりつつあります。
だから、待てないそして我慢もできません。お腹が空いたら、公共の場でもどこでもかまわず何かを食べます。家まで我慢できないと学校帰りでも買い食いをします。夕飯の準備が遅れれば、自分だけ勝手にお菓子を食べます。すべて自分の欲するままに行動し、思い通りにならないと限界が浅いからすぐキレてしまいます。それを対人関係にまで持ち込むため、トラブルも多いです。集団遊びの経験が少ないので、仲間との折り合いのつけ方や調整の仕方も苦手なようです。それぞれが勝手な行動に終始し、相手を気遣うこともできず、気ままで希薄な人間関係となりがちです。嫌いな子は徹底して嫌い、好きな子は徹底して好き、感情優先で理性的な側面はあまり見られません。したがって、行動の判断基準は客観的な善悪ではなく、個人的な好き嫌いや快楽、友人との間に互いに切磋琢磨するなどという感覚はあまり見られません。
もちろん、すべての子どもがこのような状態にあるとは思いません。しかし、まだまだ未発達な子どもたちですから、どうしても安易で楽な方向には流されやすいと思います。一方で、その心は未成熟であり、自己肯定感は低く、常に不安を抱え、傷つきやすく、悩みやすく、落ち込みやすいようです。人間関係がめんどうになると自分の殻に閉じこもってしまう恐れもあります。
このままではいけないと思います。まず、私たち大人が、子どもたちにしてあげられることから実行しなければ・・・。家庭で、学校で、地域で、さまざまな機会に「待つこと」や「耐えること」を教え、具体的に体験させていくことが必要ではないでしょうか。